はじめに
AIを業務に導入すると、「便利になる」「効率化される」という期待が先行しがちですが、その裏では新たな摩擦が生まれているのも事実です。
- うまく使えない
- 理解できない
- 信用できない
- 現場と乖離している
これらの違和感や不安は、技術そのものの問題というより、導入プロセスやユーザー体験の設計に課題があるケースが大半です。
本記事では、AI導入によって生じる“新たな摩擦”の正体と、UXがそれにどうアプローチできるかについて、UXデザイナーの視点から掘り下げていきます。
なぜAI導入は「スムーズにいかない」のか?
AIの導入は、従来のツール導入とは性質が異なります。
1. 出力の不確実性
AIは、必ずしも「正しい答え」を返すわけではなく、“もっともらしい”が“間違っている”回答も生み出します。この曖昧さが、利用者の混乱や不信感につながります。
2. ブラックボックス性
AIの判断ロジックが見えづらいため、なぜそうなったのか、なぜこの答えになったのかがわからないという摩擦が生まれます。
3. 業務構造とのズレ
AIを「既存フローにそのまま載せる」だけでは、人の判断や感覚と噛み合わないポイントが発生します。現場の期待や文化に対する設計が不十分なままだと、受け入れられません。
摩擦の種類とその背景
| 摩擦の種類 | UX上の背景 |
|---|---|
| 理解の摩擦 | UIや説明が不十分。操作意図と結果が合わない |
| 信頼の摩擦 | 出力根拠が見えない。誤答が放置されている |
| 習慣の摩擦 | 既存業務フローと統合されておらず、手間が増える |
| 期待値の摩擦 | 「なんでもできる」と思っていたが、実際は違った |
| コミュニケーションの摩擦 | 対話UIの曖昧さや脱線によるストレス |
これらは「ユーザーが悪い」のではなく、設計側が期待と体験のギャップを埋められていないことに起因する課題です。
UXができること:摩擦の“設計”と“緩和”
UXデザインは、摩擦を完全にゼロにすることではなく、「摩擦のある場所」を事前に察知し、適切に緩和・説明・改善できる構造をつくることです。
1. 前提を丁寧に伝える
「AIがどう動くか」「何ができて、何ができないか」を明示することで、期待値の調整と安心感の醸成につながります。
2. 出力に文脈や根拠を添える
RAG(検索拡張生成)を活用し、情報ソースを併記したり、「この判断の理由」「参考にした内容」を表示する設計が信頼性を高めます。
3. 操作と結果の因果を明確にする
ユーザーが何をしたら何が起きたかが直感的にわかるように、フィードバックや進行状況の可視化を工夫します。
4. 不満や誤りを即時フィードバックできる仕組み
「この回答は正確でしたか?」といった軽いフィードバック入力、エラーや改善要望を気軽に伝えられるUIは、プロダクト改善にもつながります。
実践例:社内AIツール導入のケーススタディ
ある企業では、FAQ対応をAIエージェントに置き換えるプロジェクトを進めていましたが、導入初期は「結局、人に聞いた方が早い」と言われてしまいました。
UXチームが介入し、以下の改善を行いました。
- 初回利用時に「AIが得意なこと・不得意なこと」を簡潔に案内
- 回答に参考ページと更新日を表示
- ユーザーが「意図通りだったか」を評価できるUIを設置
- 月次で“よくある失敗パターン”を分析し、シナリオを修正
結果、3ヶ月後にはAIエージェントの利用率が倍増し、社内ヘルプ業務の負担も目に見えて軽減されました。
おわりに(まとめ)
AI導入で生まれる摩擦は、避けられないものかもしれません。ですがそれは同時に、プロダクトとユーザーの間に生まれる“対話の入口”でもあります。UXデザイナーがその摩擦を丁寧に扱い、「使いづらさ」から「納得できる使い心地」へと導くことこそが、AI時代のUXの本質的な役割ではないでしょうか。
便利さの裏にある違和感や迷いに光を当てること。それは、ユーザーの声を代弁する私たちUXデザイナーの、最も大切な仕事のひとつです。
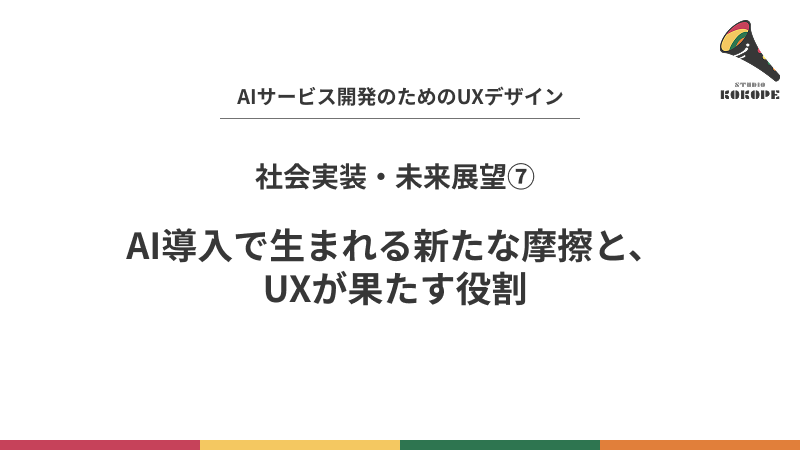
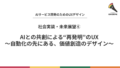
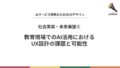
コメント