はじめに
AIエージェントをはじめとする生成AIを活用したプロダクトが広がる中で、「説明可能性(Explainability)」がUX設計において避けて通れないテーマとなっています。これは単にユーザーの安心感を高めるだけでなく、国内外で進むAIに関する法制度や規制への対応という側面もあります。特にEUのAI規則(AI Act)や日本のAI事業ガイドラインでも、説明可能性は中心的な要素として位置づけられています。
本記事では、法制度の観点をふまえながら、UXデザイナーがどのように説明可能な体験を設計するかについて解説します。
「説明可能性」が求められる背景
法制度による要請
EUのAI規則(AI Act)では、AIシステムの分類に応じて厳格な要件が定められており、「高リスクAI」には透明性と説明責任の確保が義務づけられています。日本でも2024年に改訂されたAI事業者ガイドラインにおいて、ユーザーへの適切な情報提供と判断支援の必要性が強調されています。
ユーザーの信頼確保
AIエージェントが業務プロセスに深く入り込むほど、ユーザーは「なぜこう判断されたのか?」「どのような情報を元に処理されたのか?」を知りたくなります。UXは、この説明ニーズに応える重要な接点となるのです。
説明可能性のUX的アプローチとは?
1. 透明性のあるインターフェース設計
- 出力の根拠を表示する
例:RAG(検索拡張生成)を使っている場合は、参照されたドキュメントやリンクを明示する。 - 推論過程をビジュアルで見せる
意思決定の流れや判断ロジックを、図解やステップ表示でユーザーに提示します。
2. 入力内容の確認・調整支援
- ユーザーが入力した内容がどのように解釈されたかを明示し、必要であれば調整できるようにすることで、「勝手に誤解された」リスクを減らします。
3. 誤動作やバイアスへの対策表示
- 「この出力には不正確な情報が含まれる可能性があります」などの注意喚起を表示。
- AIが出力に自信がない場合に控えめな表現や人の確認を促す文言を挿入。
4. エージェントの“人格”と能力範囲を伝える
- AIがどこまでできて、どこからはできないのか、「役割」と「制限」をはっきり提示することで、過剰な期待や誤解を防ぎます。
UXと法務の連携が鍵となる
UXデザイナーは、説明可能性を“UIの中でどう見せるか”だけで捉えるべきではありません。以下のように、法務・エンジニア・プロダクトマネージャーとの連携が不可欠です。
- 法務との連携:利用規約、プライバシーポリシー、同意設計などの文言をどうUIに落とし込むか。
- エンジニアとの連携:AIの出力に対してどのようなメタデータ(信頼スコアや参照元)を取得・表示できるか。
- PdMとの連携:説明可能性とプロダクトスピード・体験のバランスをどう取るか。
説明可能性は「義務」ではありますが、同時にプロダクト価値やユーザー信頼を高める要素にもなり得るのです。
ケーススタディ:AIエージェントの“説明インターフェース”
実際のプロジェクトでUXとして盛り込んだ機能の例を紹介します。
- AIが出力した回答の横に「根拠を見る」リンクを配置
ユーザーがクリックすると、使用されたドキュメントと該当箇所がハイライトされて表示される。 - 対話ログ上に「この提案はAIによる仮説です」と注記
人が意思決定する前提を明示し、責任の所在を曖昧にしないように工夫。 - 設定画面に「このAIの制限と注意点」ページを設け、平易な言葉で説明
長文の利用規約ではなく、UXとして読まれるインターフェースに設計。
おわりに(まとめ)
説明可能性はUXデザイナーにとって、単なる「義務対応」ではなく、ユーザーの安心と信頼を支える重要な設計領域です。法制度が進化し続けるこれからの時代において、UXは「説明責任を果たせる体験」そのものを設計する職能として、さらに注目されていくでしょう。
“わかりやすさ”と“納得感”のあるUXは、AI時代の競争力の源泉です。ユーザーと社会に信頼されるプロダクトづくりのために、法制度と向き合いながら、体験設計の観点からの「説明可能性」を追求していきましょう。
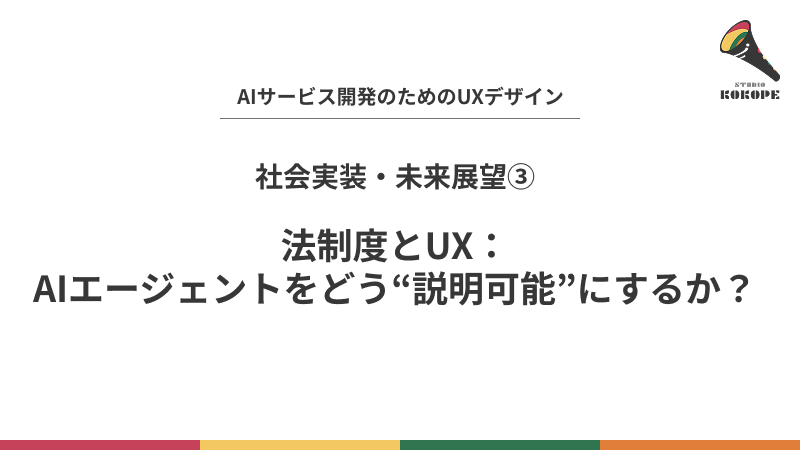
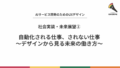
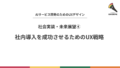
コメント