はじめに
生成AIが搭載されたプロダクトに触れたとき、多くのユーザーが最初に抱く感情があります。
「本当に合ってるの?」
「このまま任せて大丈夫?」
「なんかちょっと信用できない…」
この“ちょっとした不信感”は、機能そのものよりも、体験全体の中にある曖昧さや不安感に起因していることが少なくありません。だからこそ、UXデザイナーは単なる機能美や見た目の整合性ではなく、ユーザーとの信頼関係をどう設計するかに取り組む必要があります。
この記事では、AIサービスにおける「信頼性のUXデザイン」をテーマに、どこに不信感が生まれやすいのか、どう設計で解消していくかについて、少し探っていきたいと思います。
なぜユーザーはAIに不信感を抱くのか?
原因1:出力が不安定/正解が見えにくい
AIの回答は常に“正しい”とは限らず、同じ入力でも返答がブレる。
→ ユーザーは「信じていいのか?」と迷う
原因2:仕組みがわからない(ブラックボックス)
何を根拠に答えたのかがわからない
→ 判断や決定の「理由」が見えず、納得しにくい
原因3:勝手に進められる(コントロール感の欠如)
思ってもいないアクションや出力が返ってくる
→ ユーザーが“置いてけぼり”にされる感覚
信頼関係を築くUX設計の3つの原則
原則1:説明可能性(Explainability)を持たせる
「なぜこの出力なのか?」を説明できる構造
- 回答の出典や参照元を明示(RAG活用時など)
- AIが採ったステップを表示(ツール実行・推論手順など)
- 「このAIは〇〇をもとに動いています」とUI内で示す
UI例:
- 「この回答は〇〇マニュアルから引用しています」
- 「次にこの手順を実行します。よろしいですか?」
原則2:コントロール感(Controllability)を与える
「ユーザー自身が選べる」ことが、安心につながる
- 完全自動ではなく、「提案 → 選択 → 実行」の段階的設計
- 出力パターンの選択肢(例:カジュアル/丁寧)を用意
- 戻る/やり直す機能の明示
UI例:
- 「この案を修正しますか?」「別のアイデアを見ますか?」
- 「AIによる自動提案の度合い」をスライダーで調整
原則3:一貫性(Consistency)を保つ
「同じような問いには同じように返す」が、信頼の土台に
- 回答のトーンや語調を安定させる(プロンプト設計による制御)
- ペルソナや人格設定を統一(“秘書”なのか、“友人”なのか)
- シナリオごとの行動ロジックを設計・制限する
UI例:
- 「私は〇〇AIアシスタントです。丁寧な対応を心がけます」
- 回答のトーンを統一:「〜いたします」「〜しましょう」など
設計パターン:信頼構築のためのUXアイデア集
| UXパターン | 目的 | 実装例 |
|---|---|---|
| ステップ表示 | 不可視な思考過程を明示 | 「今〇〇を調べています → 結果:〇〇」 |
| 出典表示 | 情報の信頼性を高める | 「この回答は社内FAQから抽出されました」 |
| トーン選択 | ユーザーとの相性を調整 | 「カジュアル/丁寧/ビジネス」の選択 |
| 操作ガイド | 初回利用時の不安を和らげる | 「このAIは◯◯まで対応可能です」 |
| エラー回避UI | 失敗時のリカバリーを保証 | 「やり直す/AIに再入力させる」選択肢を用意 |
おわりに(まとめ)
信頼は、デザインできる。
それは、単に見た目や便利さの話ではなく、「このAIは、自分をちゃんと理解してくれている」「このサービスは、間違っても置いていかない」──そんな体験を、UIとインタラクションの積み重ねで実現していくこと。そして、UXデザイナーがAIとユーザーの間に立つことで、”不信感から信頼へ”、”不安から安心へ”、”コントロール不能から納得感へ”と、体験を変えていくことができます。
次世代のAIサービスに必要なのは、「すごい」ではなく「信じられる」デザインであり、その設計は、私たちの手の中にあるということです。
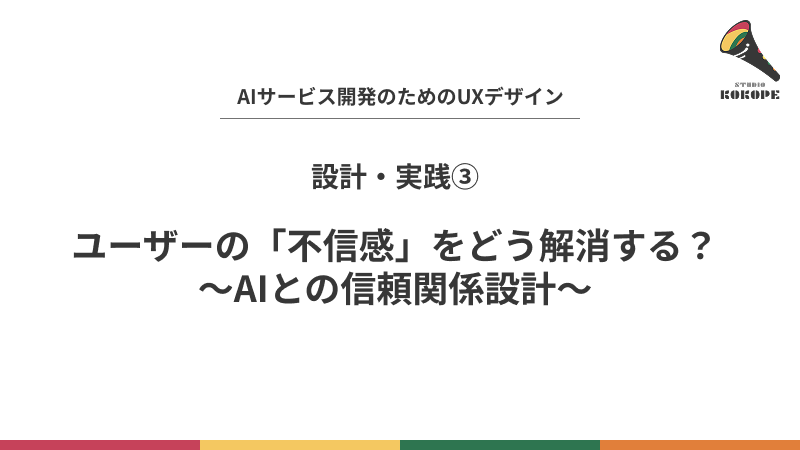
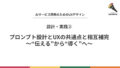
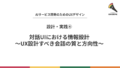
コメント