はじめに
AIサービス開発に関わるようになったけれど、用語が多すぎて会話についていけない。
そんな経験、ありませんか?
生成AIやAIエージェントを活用するプロジェクトが増える中で、「プロンプト」「LLM」「RAG」「エージェント」「トークン」…と、一見専門的なワードが日常会話にどんどん入ってくるようになりました。
UXデザイナーとしてプロダクト設計や体験設計に関わるためには、こうした用語を単に知識として覚えるだけでなく、設計のどのタイミングで活きるのかまで理解することが不可欠です。
この記事では、UXデザイナーがAIサービス開発に参加する際に理解しておくべき代表的な用語を、意味・関係性・活用場面の3点でわかりやすく解説します。
LLM(Large Language Model)
意味
大量のテキストを学習した巨大な自然言語モデル。ChatGPTやClaude、Geminiなどが代表。
関連用語
- GPT-4(OpenAI)、Claude(Anthropic)、Gemini(Google)などが代表的なLLMプロダクト
- API経由で呼び出して、質問応答や要約・翻訳・生成ができる
UXデザイナーにとってのポイント
- 「どんなLLMを使っているか」によって応答の傾向や精度が変わる
- 設計時には、モデルの制限(入力文字数、非対応タスク)や応答スタイルを把握しておくことが重要
プロンプト(Prompt)
意味
LLMに「こう返してね」と指示する入力文のこと。
例:「あなたはカスタマーサポートの担当者です。以下の内容にやさしく返答してください…」
関連用語
- システムプロンプト:LLMの性格や役割を指定する冒頭部分
- ユーザープロンプト:ユーザーの発言に該当
- ショットプロンプト:例を与えて学習的に誘導する
UXデザイナーにとってのポイント
- プロンプト設計は「UX設計の一部」。出力内容、口調、説明の長さなどに影響する
- 意図が伝わらない場合の再入力フローや、テンプレート提示のUIも含めて設計する必要あり
トークン(Token)
意味
LLM内部で扱う「単語や単語の一部」を表す単位。文字数ではなく、意味単位に近い。
関連用語
- 1トークン ≒ 英単語で1語、日本語で2〜3文字程度
- 入力と出力の合計トークン数に制限がある(例:GPT-4 Turboは128kトークン)
UXデザイナーにとってのポイント
- トークン制限により、過去の文脈が切れる/情報が欠落するリスクがある
- 「履歴のどこまでが残っているか」をUIで示すなど、状態設計が必要
RAG(Retrieval-Augmented Generation)
意味
LLMの外部にある情報(PDFやデータベース)を検索して、回答に活用する技術。
関連用語
- Embedding:検索のためにテキストを数値化する技術
- ベクターデータベース:意味ベースで類似検索するデータ構造(例:Weaviate、Pinecone)
UXデザイナーにとってのポイント
- 社内ドキュメントを参照できるAIチャットは大体この仕組み
- 情報が古い/不完全なときの「出典明示」や「補足案内」が体験として重要
- UX設計では「LLMの出力か、外部検索結果か」を明示する工夫が鍵
エージェント(AI Agent)
意味
LLMにタスク実行機能を追加し、自律的に行動させる仕組み
例:「この情報を要約して、PDFに変換して、メールで送る」という一連の流れをAIが判断して実行する
関連用語
- Tool Use:AIがツール(APIなど)を呼び出して処理する機能
- 状態管理(Memory):途中経過や目標を保持する機構
UXデザイナーにとってのポイント
- チャットボットとの違いは「行動するか、しないか」
- 複雑なタスクになるほど、ステータス表示や分岐エラー時のフォローUIが必要になる
その他の重要用語(一覧)
| 用語 | 意味 | UX上の注意点 |
|---|---|---|
| ファインチューニング | LLMの学習済モデルを特定用途向けに再学習させる | 導入・更新コストが高いため、UI変化との整合性確認が重要 |
| Embedding | 文章をベクトル化して類似検索に使う | 検索対象に抜け漏れがあると、AIの出力に偏りが出る |
| トレースログ | LLMやエージェントの動作記録 | ユーザーに「なぜその出力になったか」を説明する際に役立つ |
| ガバナンス | 情報管理やセキュリティ、正確性の担保 | UI上でも「AIにできないこと」を明示する必要あり |
おわりに(まとめ)
AIサービスの開発において、用語の理解は「実装」だけでなく「体験設計」にも直結しています。
UXデザイナーは、単にUIを整えるのではなく、
- LLMの仕様を前提にした導線や表現の設計
- プロンプトが生む誤解を防ぐ入力支援UI
- トークン制限やRAG精度の限界を補う補足設計
といった形で、技術とユーザーの橋渡しをする役割が求められます。
今後さらに複雑で高度なAIプロダクトが増える中で、言葉と仕組みを「デザインの視点」で理解していることが、真のUX価値につながるはずです。
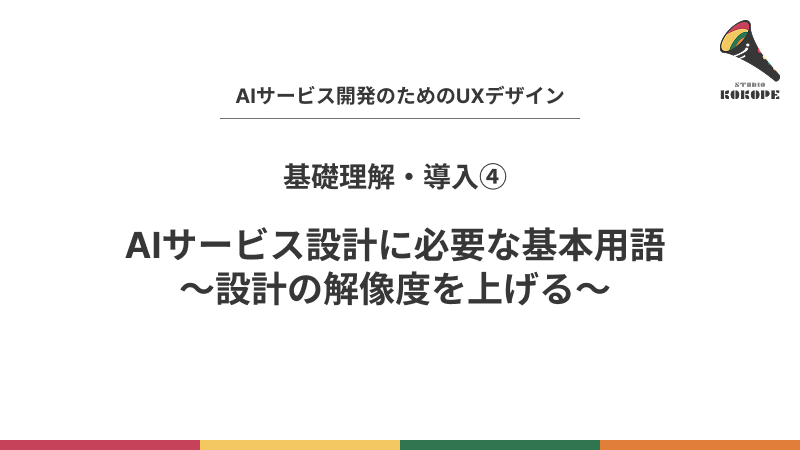
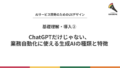
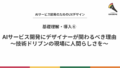
コメント