はじめに
AIができることは増えた。でも、本当にAIに任せるべき「業務」とは何か?
生成AIやAIエージェントを使った業務自動化が進む中で、「どの業務をどう自動化するべきか?」という問いに直面する機会が増えています。そんな中において私たちUXデザイナーは、単に画面を設計するだけでなく、「業務そのもの」を再設計する立場として関わることが求められています。
本記事では、業務自動化の現場でよく話題になる職種別のユースケースを取り上げながら、UX観点での課題や可能性について述べています。
自動化を考える前に必要な“業務の可視化”
そもそも、どんなに高性能なAIを使っても「何を任せるか」が曖昧なままでは成果は出ません。UXデザインのプロセスにおいても、業務プロセスの見える化(As-Is / To-Be)は基本中の基本になります。
具体的には以下のような観点から業務を分類して考えます。
| 分類軸 | 内容 |
|---|---|
| 頻度 | 毎日〜週次〜月次 |
| ルール化のしやすさ | 手順が決まっている/毎回判断が必要 |
| データとの関係 | 入力系・整理系・出力系 |
| 利用者の熟練度 | 属人性が高いか/マニュアル化されているか |
| 心理的負担 | 面倒/時間がかかる/集中力がいる |
職種別ユースケースとUX観点の考察
ここからは代表的な職種を5つ取り上げ、それぞれにおける自動化のユースケースと、UX上の注意点を紹介したいと思います。
営業(Sales)
ユースケース例
- 商談メモの自動記録とCRM入力
- 提案書やメール文面のたたき台生成
- アポ調整・日程候補提示の自動化
UX観点のポイント
- 自動生成された内容をそのまま使うことはないが、下書きがあることで大幅な時短になる
- ミスが成果に直結する職種のため、AIへの信頼性と確認導線の設計が不可欠
- 自動化によって「時間が浮いた」実感をユーザーに与える演出が大切
カスタマーサポート(CS)
ユースケース例
- よくある質問の自動回答(AIチャット)
- クレーム傾向の要約・集計
- 対応履歴からのトーン最適化提案
UX観点のポイント
- 対応スピードと正確性のバランスが鍵
- 不安や怒りの感情が絡むため、「機械的で冷たい」と感じさせないUX演出が必要
- 対話型AIは人格や言葉遣いのデザインで体験が大きく変わる
マーケティング(Marketing)
ユースケース例
- 過去の施策から傾向を分析+提案文を生成
- SNS投稿案のアイデア出し支援
- レポートやKPIダッシュボードの要約作成
UX観点のポイント
- 出力内容に対して「編集したくなる余白」を残す設計が効果的
- クリエイティブ系業務では、「発想のきっかけ」としての使い方が多いため、即出力よりも「選べる」体験が好まれる
- 結果だけでなく「プロセスの見える化」も意識したUIが求められる
経理・バックオフィス(Admin)
ユースケース例
- 領収書のOCR読み取りと仕訳提案
- 定型レポートの自動生成
- 勤怠データからの月報自動作成
UX観点のポイント
- 「間違えてはいけない」性質上、AIによる提案の「根拠表示」が不可欠
- エラー時の手動修正プロセスをUXとして丁寧に設計する必要がある
- 「手戻りが面倒」と思わせないUI遷移設計が信頼感につながる
人事・採用(HR)
ユースケース例
- 履歴書スクリーニング
- 面談記録の要約
- 求人票の草案作成
UX観点のポイント
- 候補者の印象・評価など「定性情報」が多く、人間の判断が不可欠
- 自動化は「補助」に留め、評価・判断は人間側に明確に残す設計が望ましい
- 関係者間(人事・現場)の情報共有のUXを整備することで、効果が最大化される
共通するUX課題とデザインの役割
どの職種においても、AI導入の鍵は「どこまで任せて、どこで人が介入するか」の線引きにあります。
UXデザイナーが担うべき役割は、このバランス設計と、ユーザーの心理に寄り添った導線づくりです。
UX的なポイントまとめ
- 「完全自動」ではなく「補助ツール」として見せるUI設計
- ユーザーの不安を軽減する「説明可能性」や「修正しやすさ」
- 成果が出たことを可視化する「手応え設計」
- 導入初期のオンボーディングで「使える実感」を持たせる演出
おわりに(まとめ)
業務自動化というと「どこまでAIに任せるか?」が議論されがちですが、本質的には「人が力を発揮できる領域を、どう残すか?」の話だと思っています。
UXデザイナーの私たちにできることは、単に業務を自動化することではなく、その自動化が「人にとって心地よい」か、「意味のある変化」かどうかを考えることです。
業務プロセスそのものを「再設計」する視点を持ちながら、AIと人が共に働く未来の基盤をつくっていくことが大切です。
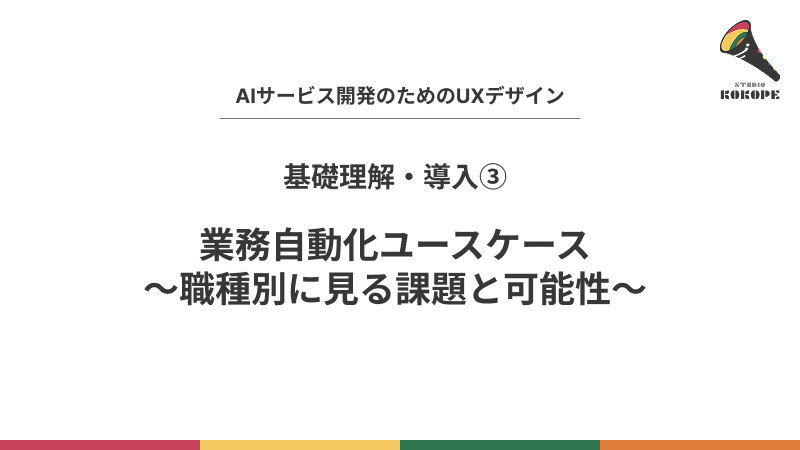
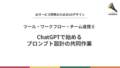
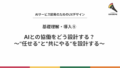
コメント