こんにちは。UXデザイナーの toma です。
現在、私はAIエージェントを活用した業務自動化プロダクトに、UXデザイナーとして参画しています。仕事の現場においてAIを活用する機会が急速に増える中、いよいよそのサービスの立ち上げから関われることになり、大きな希望とともに身の引き締まる思いでいます。
AIというと、技術的な専門領域に感じるかもしれませんが、だからこそUXの視点が必要とされる場面が数多くあると感じています。その考えのもと、今回、「AIエージェント」を軸としたUXデザインに関する記事をシリーズ化して書いてみることにしました。
このシリーズは、私と同じようにAIサービスの現場に関わるUXデザイナーの方々に向けて、以下の5つのテーマに沿って体系的にまとめたものです。
すべての記事は、現場の視点とデザイン実務の手触り感を大切にしながら構成しています。
少しでも、AI時代においてUXデザイナーが自分の専門性を活かし、開発現場で力を発揮するための一助になれば幸いです。
はじめに
プロダクトを「つくるだけ」では終われない時代。
業務改善においてAIの活用が加速する中、業務自動化の文脈で注目されているのが「AIエージェント」という言葉です。私自身も現在、AIエージェントを活用した業務自動化プロダクトの開発に関わるUXデザイナーとして、日々この技術と向き合っており、どうすれば技術のより良い活用ができるか、新しい価値を生み出せるか、毎日試行錯誤を繰り返しています。
本記事では、「そもそもAIエージェントとは何か?」というところから、UXデザイナーがどのように関われるのか、どんな視点が求められるのかを中心にお伝えします。エンジニアではなくデザイナーが語るAIガイドとして、今後のプロジェクトや学習の土台になればと思います。
AIエージェントとは?
AIエージェントとは、ユーザーの目的達成のために「対話しながら、考え、行動できる」自律型のAIシステムです。キーワードは「自律性」「対話性」「ツール実行能力」。
例えば、ユーザーが「会議を調整して」と言えば、AIエージェントはカレンダーを確認し、メールを作成し、社内システムと連携してタスクを完了してくれます。これは、従来の単発的なチャット応答とは一線を画します。
構成としては以下の要素が合わさって動作しています。
- LLM(大規模言語モデル):自然言語を理解・生成する頭脳部分。ChatGPTやClaudeなど。
- ツール実行:APIやデータベースとの連携により、システム上のアクションを起こす能力。
- 状態管理:ユーザーとの過去のやり取りや目標を記憶・参照して文脈を保ち続ける機能。
つまり、話すだけで終わらず「動く」AIがAIエージェント。ユーザーの意図を汲み取り、複数の手順を経て成果を出す、そのプロセス全体を担う存在です。
チャットボットとの違い
「AIエージェントって、チャットボットの進化版でしょ?」と聞かれることがあります。確かに似ている部分もありますが、根本的な違いは「目的志向性」と「自律性」にあります。
| 観点 | 従来のチャットボット | AIエージェント |
|---|---|---|
| 対応の範囲 | 事前定義された質問と回答のやりとり | 曖昧な問いに対しても柔軟に応答し、最適な行動を選択 |
| 動作の範囲 | FAQ表示や予約システム連携など単機能 | 複数ツールを連携し、一連の業務を自動実行 |
| 判断力 | ルールベース(if-then) | 推論ベース(プロンプト+LLM) |
| 状態の保持 | セッション単位で終了 | 長期的な文脈や履歴を記憶し活用 |
デザイナーとして重要なのは、チャット「体験」をつくるのではなく、「行動体験(Actionable UX)」を設計することへのシフトです。
デザイナーが関わるポイント
AIエージェントは技術的にはエンジニアリング主導に見えがちですが、UXデザイナーの出番はむしろ増えています。なぜなら、ユーザーの体験が「見えづらい」からです。
以下は私自身が関わってきた中で重要だと感じているUXの接点です。
インタラクション設計
- 会話の自然さ、選択肢の提示、ユーザーの入力補助など、人との接点をどう設計するかが重要。
- 誤解や不信を生まないように、「言葉の使い方」や「言い回し」に配慮します。
プロンプト設計支援
- UXライティングの延長として、ユーザーの意図がAIに正確に伝わるように入力パターンを設計。
- プロンプトのテスト・バリエーション出しもデザイナーが関与できます。
業務理解とタスク設計
- ユーザーの業務プロセスを可視化し、どの工程をAIに任せるかをマッピング。
- 「自動化する/しない」の線引きをユーザー体験視点で行うことが鍵になります。
実例で見るAIエージェントの働き方
以下は、実際に導入が進んでいるAIエージェントのユースケースです。
営業アシスタント
営業担当のメール内容や商談記録をもとに、要点をまとめてCRMに登録。さらに、次回のアクション候補を提案してくれる。
→ 作業の短縮だけでなく「次の一手」を後押しする体験設計が重要。
社内ヘルプデスク
Slack上で「VPNつながらない」と打てば、マニュアルを検索し、該当手順を提示。そのまま申請フォームまで案内してくれる。
→ マニュアルのUX+導線設計の最適化が問われます。
マーケティング支援
過去のLPや広告文のパフォーマンスを分析し、新しいコピーの草案を生成。さらにABテスト候補として複数パターンも提案。
→ 単なる文生成ではなく、「選べるUX」や「文脈表示」が体験価値になります。
デザイン観点での課題と展望
AIエージェントは可能性に満ちていますが、まだまだ課題も山積しています。以下は、デザイナーの視点で特に重要と感じているテーマです。
信頼の設計:AIが間違える前提で考える
- 完全自動ではなく「人が判断できるように支える」設計が大切。
- 出典表示、手戻りの選択肢、Undo設計などが信頼の鍵。
可視性と期待値コントロール:何ができるかをユーザーに伝える
- ユーザーは「これもやってくれるの?」と戸惑いがち。
- ガイドライン/プレビューUI/説明文の設計で期待値調整を支援。
継続利用に向けて:“手応え感”のあるUIをどう作るか
- 自動化=見えない操作、だからこそユーザーに「働いてくれた」感覚を与える視覚的・聴覚的フィードバックが必要。
将来性と持続性:誰でも使えるAIのために
- 高度な機能を「誰でも迷わず使える」ようにするのがUXの役割。
- マルチモーダル対応やアクセシビリティの観点も今後はより重要に。
おわりに(まとめ)
AIエージェントは、単なるチャットやFAQの延長ではありません。「業務の共演者」として、ユーザーとともに働く存在です。そんな未来をデザインするには、UXデザイナーの力が必要です。私自身も学びの途中ですが、このシリーズを通して、「デザイナー視点から見るAI」の理解と応用の一助になれればと思っています。
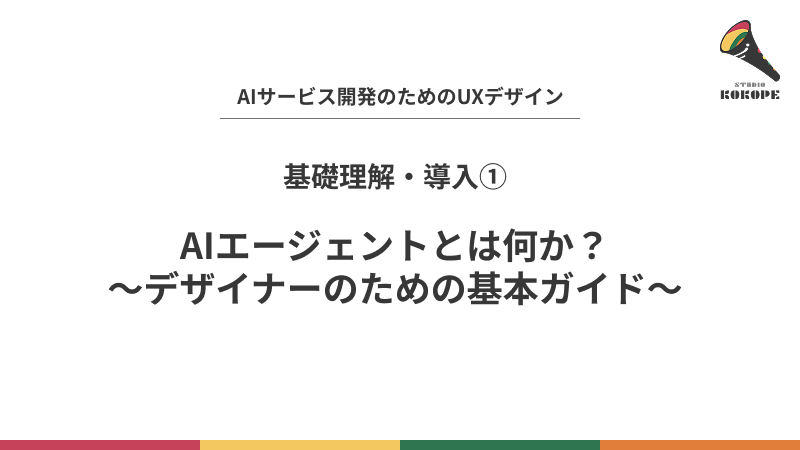
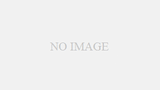
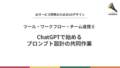
コメント