はじめに
色は人によって見え方が違う──
デザインにおいて「色」は強力な表現手段です。しかし、すべての人が同じように色を知覚しているわけではありません。日本人男性の約5%、女性の約0.2%は先天的な色覚特性(いわゆる色弱)を持つと言われています。さらに、加齢や環境要因によっても色の見え方は変わります。
つまり、配色を考えるときには「色の美しさ」だけではなく「色が正しく伝わるか」「色だけに依存していないか」という観点が欠かせません。アクセシビリティを考慮した配色は、誰もが安心して使えるプロダクトをつくるための基本なのです。
色覚特性を理解することから始める
色の見え方の多様性
色弱と一口に言っても、その種類や程度はさまざまです。代表的なものは以下のとおりです。
- 1型(赤系の識別が困難):赤と緑の区別がしにくい
- 2型(緑系の識別が困難):こちらも赤と緑が混同されやすい
- 3型(青系の識別が困難):青と黄色の区別が難しい
これらは「色相が区別しにくい」だけでなく、「明度や彩度の差を捉えにくい」ケースもあります。つまり、単純に「色を変えればいい」という話ではなく、複合的な工夫が求められます。
誰にとっても影響がある
色弱の有無に限らず、次のような状況でも色の見え方は変わります。
- 太陽光や蛍光灯など、光源の違い
- スマホ画面の明るさや省エネモード
- 高齢によるコントラスト感度の低下
こうした環境や身体的な要因を踏まえれば、「誰でも見やすいデザイン」を目指すことは必然であるとわかります。
色だけに頼らない情報設計
複数の手がかりを組み合わせる
色は情報を区別する便利なツールですが、唯一の判断基準にしてしまうと危険です。たとえばグラフの凡例で「赤=売上、緑=コスト」と示しても、色弱ユーザーには見分けがつかない可能性があります。
そこで重要なのは「色以外の手がかり」を併用することです。
- 形状の違い:折れ線、点線、棒のパターンを使い分ける
- テキスト表示:数値やラベルを明示する
- アイコンの利用:矢印やシンボルで意味を補足
こうした工夫を取り入れることで、誰にとっても情報が理解しやすくなります。
ボタンやリンクの識別
「青文字はリンク」という慣習がありますが、色弱の人にとっては「青」と「黒」の区別が曖昧な場合もあります。そのため:
- 下線を必ず付ける
- ホバー時に形状や影を変える
- アイコンを付与する(▶、+など)
といった工夫をすると、色に依存しない操作性を実現できます。
配色時に考えるべきコントラスト
視認性を左右する「コントラスト比」
色覚特性を持たない人でも、背景と文字のコントラストが弱いと読みづらくなります。アクセシビリティ基準(WCAG)では、テキストの可読性を確保するために以下のコントラスト比を推奨しています。
- 通常のテキスト → 4.5:1 以上
- 大きな文字(18pt以上) → 3:1 以上
例えば「薄い灰色の文字 × 白背景」はコントラスト不足で読みにくく、ユーザーの離脱を招く要因になります。
実務でのチェック方法
- チェックツールを使う:Color Contrast Analyzer など
- モノクロ表示で確認:スマホやPCで白黒表示に切り替えて見分けがつくか確認
- チームでレビュー:異なる環境・人の視点で画面を見てもらう
これらを習慣化することで、配色の質が安定します。
チームでアクセシビリティを考慮する方法
デザインシステムにルール化する
アクセシビリティ対応は、個人の意識だけに頼ると抜け漏れが発生します。そこで、配色ルールをデザインシステムに組み込むことが重要です。
- ブランドカラーの使用範囲 → メインボタンに限定
- 警告色(赤・黄・緑) → コントラスト基準を満たす値に調整
- リンク表現 → 色だけでなく下線・アイコンを必ず付与
こうしたルールをチーム全体で共有することで、アクセシビリティ対応が標準化されます。
実際のユーザーに検証してもらう
ツールでのチェックだけでは限界があります。最終的にはユーザーテストで「実際に見えるか・使えるか」を確認することが欠かせません。特に以下のような場合──
- 色弱ユーザーへのインタビューや操作観察
- 高齢ユーザーによる可読性テスト
- 多様な環境(屋外・夜間・低輝度モード)での利用確認
こうした検証を重ねることで、単なる「ルール上の合格」ではなく、本当の意味で誰にとっても使いやすい体験が実現できます。
おわりに(まとめ)
アクセシビリティを考慮した配色は、特別なユーザーだけのためではありません。それはすべての人にとって「安心して使える」体験をつくるための基本です。
- 色覚特性を理解し、色の見え方が人によって違うことを前提にする
- 情報は「色だけ」で伝えず、形やテキストを併用する
- コントラスト比を意識し、誰でも読みやすい文字・背景を設計する
- チーム全体でルール化し、実際のユーザー検証で確かめる
これらを実践することで、プロダクトはより多様なユーザーに受け入れられ、結果としてビジネスの信頼性や利用価値も高まります。
色は「デザインの装飾」ではなく「体験の基盤」。アクセシビリティを考慮した色使いは、その意識をチームで共有する最初の一歩となるのです。
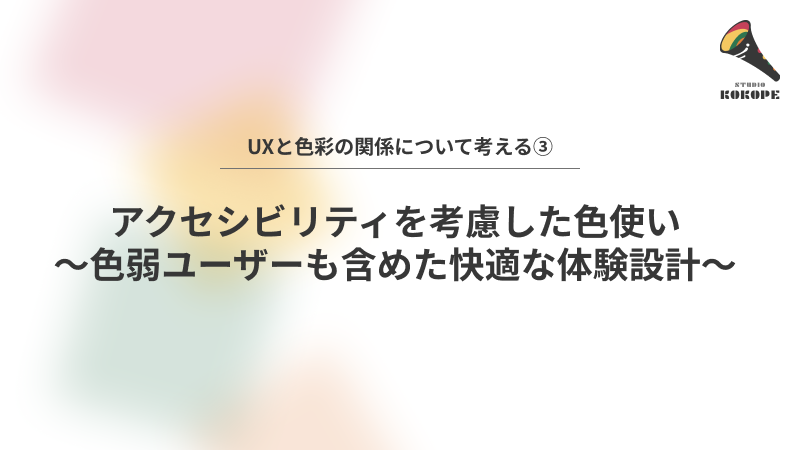
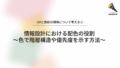
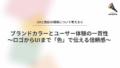
コメント