はじめに
UXデザインというと、「サービスをどう始めるか」「どう継続利用してもらうか」に意識が集中しがちです。しかし、サービスには“終わり”もあります。終了や乗り換え、解約といったフェーズにおいても、ユーザーとの関係性は続いています。特に、AIエージェントや業務自動化サービスのように、ユーザーの業務や行動に深く入り込むサービスでは、終了時の体験設計がユーザーの感情や信頼に強く影響します。
本記事では、サービス終了フェーズにおけるUX設計の重要性と、そのアプローチについて考えていきます。
「終了」は突然やってくるもの
サービス終了にはさまざまな理由があります。
- 事業戦略の転換によるサービス終了
- サブスクリプションの解約
- 一時的な機能停止や縮小
- ユーザーによる利用停止(離脱)
これらに共通しているのは、「終わり」は利用者にとっても一つの体験の区切りであるということです。にもかかわらず、UX設計が軽視されやすい領域でもあります。
終了時に生まれやすいユーザーの感情
サービス終了は、以下のような感情を引き起こすことがあります。
| 感情 | 背景 |
|---|---|
| 不安 | データはどうなるのか?他の選択肢はあるのか? |
| 喪失感 | 長く使っていたサービスが突然なくなる |
| 怒り | 代替案が提示されていない、急な告知で混乱した |
| 無力感 | 自分の意志ではどうにもできなかったという感覚 |
これらを放置すると、ユーザーとの関係性が断絶された印象を与えるだけでなく、ブランド全体への信頼にも傷がつく可能性があります。
UXデザイナーが考えるべき設計視点
1. 終了のストーリーを“体験”として設計する
サービス終了は単なる「機能の停止」ではなく、一連のストーリーと捉えるべきです。
- なぜ終了するのか
- いつまで使えるのか
- その後どうすればいいのか
これらをユーザーの感情に寄り添ったトーンで丁寧に伝えることが重要です。
2. データ引き継ぎやダウンロードの導線設計
ユーザーが自分のデータにアクセスできるよう、
- CSVやPDFでのエクスポート機能
- API連携による他サービスへの移行案内
- バックアップの自動通知
など、「これまでの利用を無駄にしない」ための配慮が信頼を保ちます。
3. 感謝とフィードバックの機会を設ける
「これまでのご利用ありがとうございました」というシンプルなメッセージとともに、
- 終了前アンケート
- 他サービスの提案
- 利用実績の振り返り(例:「あなたがこのAIで自動化した作業は累計○件でした」)
といった要素が、ポジティブな「余韻」を残します。
4. 「戻ってくる道」を用意する
完全にサービスが終了するわけではない場合、
- 機能縮小版への移行
- 別ブランドでの再開告知
- メールアドレス登録による再開通知受付
といった“戻ってくる導線”を用意しておくこともUXの一部です。
実例:業務支援AIツールの段階的クローズ
ある業務支援ツールでは、AI機能の一部を段階的に終了することになりました。UXチームが行った施策は以下のとおりです。
- ユーザーセグメントごとに異なる終了アナウンス文面を作成
(利用頻度が高い人には「お礼+代替案」、ほとんど使っていない人には「簡潔な案内」) - Notionで「移行ガイドブック」ページを作成
- ユーザーの自動化フローをPDF形式で保存・閲覧可能に
- 最後に「あなたの自動化時間、累計57時間を削減しました」という実績表示
このような取り組みにより、多くのユーザーから「ちゃんと気持ちに寄り添ってくれた」と高評価を得られ、ブランド全体への印象を損なうことなく終了を迎えることができました。
おわりに(まとめ)
UXデザインは、「はじまり」や「利用中」だけの仕事ではありません。「終わり」こそが、そのサービスの“体験の質”を決定づける場面でもあります。ユーザーにとって、あるサービスが人生の一部だったり、業務に不可欠な存在だったりすることも珍しくありません。だからこそ、その別れを丁寧に設計することには、深い意味があります。
「このサービス、最後まで気持ちよく使えた」そう思ってもらえる体験こそが、次につながる信頼となるのです。
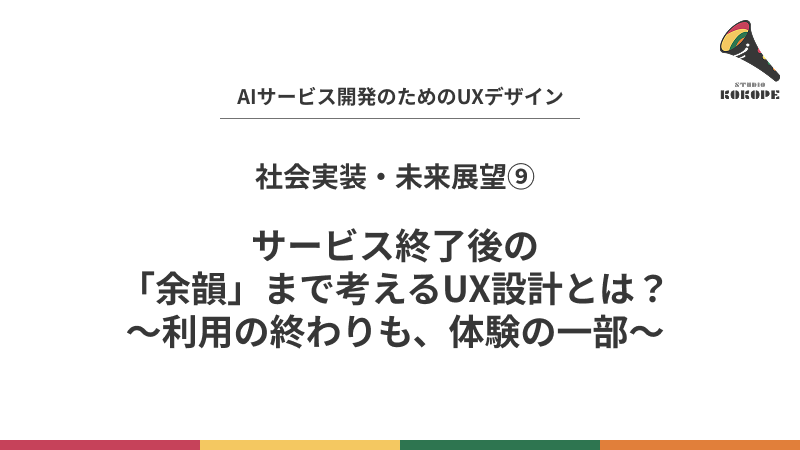
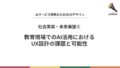
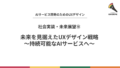
コメント