はじめに
業務自動化の潮流のなかで、AIは「省力化」「効率化」の文脈で語られることが多い存在です。しかし、AIを単なる“業務の代替手段”として使うだけでは、既存の構造のなかに新しい技術を押し込めているだけかもしれません。
本来、生成AIやAIエージェントの登場は、私たちの“仕事観”や“働き方の構造”そのものを問い直すきっかけになるはずです。それはすなわち、UXデザイナーにとって「既存業務をどう再定義し、再発明するか」という創造的な挑戦でもあります。
本記事では、AIとの共創によって業務を“再発明”するためのUXのアプローチについて掘り下げます。
自動化=改善ではない、という視点
「これまで人がやっていた業務をAIに置き換える」このアプローチ自体は悪くありませんが、それだけでは“同じことを速くやる”だけにとどまります。UXデザインの視点では、次のような問いを立てることが重要です。
- そもそもこの業務、本当に必要なのか?
- 今までのフローは、誰の何のために存在していたのか?
- AIによって「できるようになったこと」は何か?
業務を単にAIに“やらせる”のではなく、“変える”ための視点こそがUXの役割です。
再発明のための3つのアプローチ
1. 業務の“意味”を問い直す
まず必要なのは、既存業務の背後にある目的や価値を再解釈することです。
例:
- 週次レポートを自動生成する → レポートはなぜ存在するのか?
→ 実は「関係者間の認識共有」が目的。ならばレポートではなく対話型アシスタントの方が有効かもしれません。
2. “人”と“AI”の協働構造を設計する
業務を再定義するとは、役割分担の再構築です。
- 人が判断し、AIが下準備をする
- AIが案を出し、人が選択・編集する
- AIが継続的に学び、人がフィードバックを与える
協働のパターンを設計することが、新しい業務の姿をつくる鍵になります。
3. アウトプットではなく“体験”を再設計する
アウトプットだけに注目するのではなく、ユーザーがどのようにAIを使い、どんな感覚で仕事を進められるかを体験として設計します。
- 確信を持って提案できるようになる
- 作業から解放され、企画に集中できる
- チーム内の役割分担が変わり、コラボレーションが加速する
これらはすべてUXとして設計できる領域です。
実例:ドキュメント作成業務の再発明
ある企業では、営業資料の作成に多くの時間を割いていました。生成AIの導入により、以下のような「再定義」が行われました。
- 従来:資料は営業担当がPowerPointでゼロから作る
- AI導入後:
- 会話ログや顧客情報をもとに、AIがドラフト資料を自動生成
- 営業は資料作成ではなく「顧客課題に対する提案」の精度向上に集中
- 結果的に、資料ではなく「提案のロジックそのもの」が主役に
このように、AIによって仕事の“意味”が変化し、UXとしての体験価値も刷新されたのです。
デザイナーが担う「再発明」プロセスのファシリテーション
AIの力を活かした業務再設計には、次のようなステップが有効です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 業務の棚卸し | フロー図やMiroなどを用いて、現行業務を可視化する |
| ② 課題の抽出 | 工数・心理的負担・属人化など、UX観点でのボトルネックを整理 |
| ③ 再定義の検討 | 「そもそもこの業務、何のためにあるのか?」という問いを立てる |
| ④ AI活用の設計 | LLM・RAG・ノーコード連携などを使った新しい形を模索 |
| ⑤ 体験の検証 | プロトタイピング → ユーザーテスト → 現場フィードバックの循環 |
これらを進める上で、UXデザイナーは“共創ファシリテーター”としての立ち位置が求められます。
おわりに(まとめ)
業務の「効率化」を超えて、「意味の再発見」や「仕事の再構築」に踏み込むこと。それが、AI時代におけるUXデザインの真の挑戦だといえます。再発明とは、単なる機能の置き換えではありません。人とAIの協働が生み出す“新しい仕事のカタチ”をデザインすることなのです。
今こそ私たちは、目の前の業務を「変えずに効率化する」のではなく、「ゼロから再設計する勇気」と、「体験を問い直す想像力」を持って取り組んでいく必要があるのではないでしょうか。
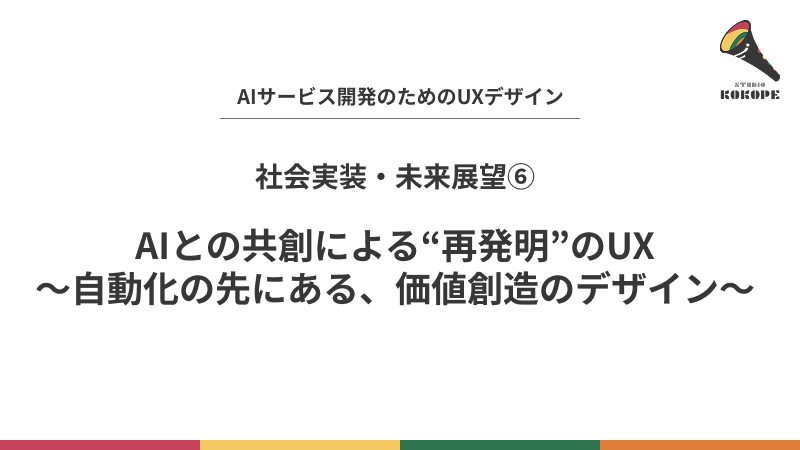
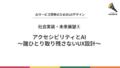
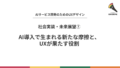
コメント