はじめに
プロトタイピングは、UXデザイナーにとってアイデアを「形」にする最初の一歩です。従来は、UIをFigmaなどで描き、場合によってはコードで動きを加えながら設計を深めてきました。
しかし今、生成AIを用いることで、プロトタイピングのフェーズにも大きな変化が訪れつつあります。本記事では、生成AIをプロトタイピングに組み込むことで得られる効果と、実験的なワークフローの事例を紹介します。
なぜプロトタイピングにAIを使うのか?
プロトタイピングに生成AIを取り入れる最大の利点は、試行錯誤のスピードが圧倒的に上がることです。従来の手法では時間がかかっていた以下の作業を、AIが補助・代替してくれるようになります。
- UIラベルやコンテンツの自動生成
- ユーザーインタビュー内容からのニーズ抽出
- ユースケースに応じた画面構成案の提案
- ワイヤーフレームのテキストベース生成(HTML/CSS/Reactなど)
これにより、「とりあえず作って試す」サイクルが高速化され、仮説検証の密度が高まるのです。
ワークフロー例:Figma + ChatGPT + 自動化ツール
以下は筆者が実際に試行している、生成AIを組み込んだプロトタイピングの実験的ワークフローです。
ステップ1:プロンプトブレスト(ChatGPT)
- サービスのコンセプトやユーザーストーリーを投げて、構造案を生成
- 例:「新しい習慣形成アプリの初期オンボーディング画面を3パターン考えて」
ステップ2:構造案をもとにFigmaでワイヤーフレーム作成
- ChatGPTから得た画面構成や文言を、Figmaでワイヤー化
- コンポーネントを再利用できるように、軽く設計ルールを作成
ステップ3:UI文言やマイクロコピーをAIでブラッシュアップ
- 各ボタンや説明文に、複数のバリエーションを生成
- 「A/Bパターン案を出してもらう」なども有効
ステップ4:プロンプト → コード出力(簡易的にHTML化)
- 必要に応じて、FigmaのワイヤーをもとにChatGPTでコード化
React + Tailwindなどの構成で、開発チームとの接続も意識
ステップ5:Miroでフロー図を整理し、チームレビュー
- 会話フローや分岐、状態管理をビジュアル化
- AI案とデザイナー案のハイブリッド提案として提示
導入時の注意点
生成AIを活用するうえでの注意点もあります。
- そのまま使えるとは限らない
→ 出力されたアイデアは「たたき台」として扱い、UX観点で必ず精査する - 意図が伝わりにくい場合がある
→ プロンプト設計のスキルが問われるため、定期的に改善するクセを持つ - 反復的な手直しが必要
→ 正解を求めるより、「対話しながら方向性を整える」姿勢が大切
チームでの活用とナレッジ共有
生成AIをプロトタイピングに取り入れると、個人の創造プロセスがより開かれたものになります。AIとのやり取りをナレッジとして残すことで、チーム内でのアイデア共有がしやすくなります。
- Notionで「プロンプトログ」を共有
- Slackで「AI案フィードバック」スレッドを設ける
- Figma上に「AI出力案」の注釈を加えてチームレビューする
こうした工夫によって、プロトタイピング自体が学習と共有のプロセスになるのです。
おわりに(まとめ)
生成AIは、あくまで創造の相棒です。UXデザイナーに求められるのは、AIが出力したアイデアを「体験」として意味のある形に仕立て直すことです。従来よりも短いサイクルで、多様な仮説を検証できるようになることで、UX設計はより動的で、探索的なフェーズにシフトしていくでしょう。
AIを使ってプロトタイピングを加速させるというのは、単なる効率化ではなく、より多くの可能性を試すための「創造的コラボレーション」に他なりません。ぜひ、小さく試しながら、あなたのプロトタイピングにもAIを取り入れてみてください。
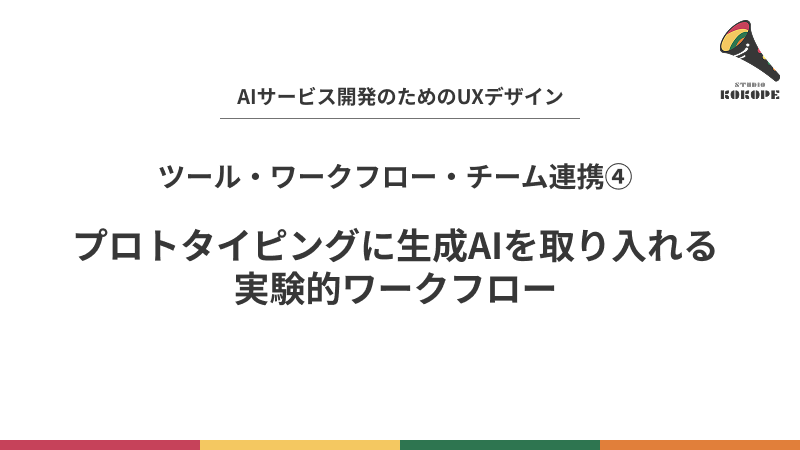
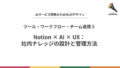
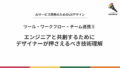
コメント