はじめに
AIを活用した業務自動化やナレッジ支援が注目される中で、そもそも前提となる「ナレッジ」が社内でうまく整備されていないケースは少なくありません。特にNotionのような柔軟な情報管理ツールを使っている組織では、情報の自由度が高い分、「どこに何があるのか分からない」「情報が更新されず陳腐化する」といったUX上の課題が起こりやすくなります。
本記事では、Notionを活用したナレッジ設計・運用の基本と、AI検索やAIエージェントとの連携を見据えたUXの考え方を紹介します。
なぜ「ナレッジのUX」が重要なのか?
情報そのものがあるだけでは、ナレッジとしては機能しません。利用者が迷わず探せて、信頼できて、再利用できる状態になってはじめて、「使える知識」と言えます。
UXデザインの視点で見れば、社内ナレッジには次のような観点が必要です。
- 発見可能性(Findability):必要なときに、すぐ見つかるか
- 理解しやすさ(Readability):誰でも読んで理解できるか
- 信頼性(Credibility):更新日や根拠が明示されているか
- 接続性(Contextuality):他の知識とのつながりが見えるか
これらを意識せずに情報を蓄積してしまうと、「溜まってはいるけど、誰も使っていないデータベース」になってしまいます。
Notionで社内ナレッジを設計するステップ
1. 情報タイプの分類
まずは、情報を以下のような性質で分類しておくと、整理しやすくなります。
- 手順系:操作マニュアル、チェックリスト
- 思考系:議論ログ、アイデア、ふりかえり
- 記録系:議事録、KPIログ、分析結果
- FAQ系:よくある問い合わせ、注意点
それぞれに適したテンプレートや更新ルールを設けることで、混在・迷子化を防ぎます。
2. トップページと検索性の設計
- ナビゲーション構造を浅くしすぎない(分類が曖昧になる)
- タグ・プロパティを必ず活用(部署、プロジェクト、作成者など)
- 検索に頼りすぎず、一覧性も担保する(定期的なディレクトリ整理)
3. 更新・運用の仕組み化
- テンプレート化して記載のばらつきを減らす
- 更新日や責任者プロパティを明記する
- 週次・月次で棚卸しやリンク切れのチェックを仕組みに組み込む
Notionは柔軟であるがゆえに、構造化・ルール化の設計がUXを大きく左右します。
AIとの連携を見据えた設計ポイント
将来的にAI検索(RAGなど)や社内エージェントを導入する際には、以下のような観点でナレッジの設計を進めておくと有効です。
1. 一貫性のある構造(スキーマ)
- ページのタイトル、構造、セクション名が統一されている
- セクションごとの意味が明確(例:「目的」「手順」「注意事項」)
これは、AIが正しく情報を読み取り、文脈を理解するために重要です。
2. メタ情報の明示
- 「これは◯◯業務に関する情報」「この内容は2025年8月時点」といった情報の範囲・前提・有効性をプロパティで持たせる
3. 情報の“断片化”とリンク設計
- 長大な1ページにまとめず、小さなナレッジをリンクで構造化する
- 関連トピックへの相互リンクや「関連ページ」セクションの設置
AIにとっても、人間にとっても、「点」ではなく「面」としての情報設計が効果的です。
ユーザー視点を忘れない設計へ
Notionは優れたツールですが、設計思想がなければすぐに使いにくくなります。UXデザイナーの視点としては、次のような問いを常に持ちながら構築を進めることが大切です。
- この情報、誰のどんなタイミングで使われる?
- この情報、初めて読む人でも理解できる?
- 情報をたどった人が、次に見るべきページへ自然に進める?
こうした問いかけを通じて、「読まれる・使われる・育てられるナレッジ」が生まれていきます。
おわりに(まとめ)
ナレッジ管理は、一度作って終わるものではなく、日々の運用と改善が不可欠な「プロダクト」です。UXデザイナーは、Notionというツールを超えて、組織内の知識体験(Knowledge Experience)全体を設計する存在として、今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。また、AIと組み合わせることで、ナレッジは「探すもの」から「活かすもの」へと進化します。そのための基盤づくりを、いま目の前の設計からはじめていきましょう。
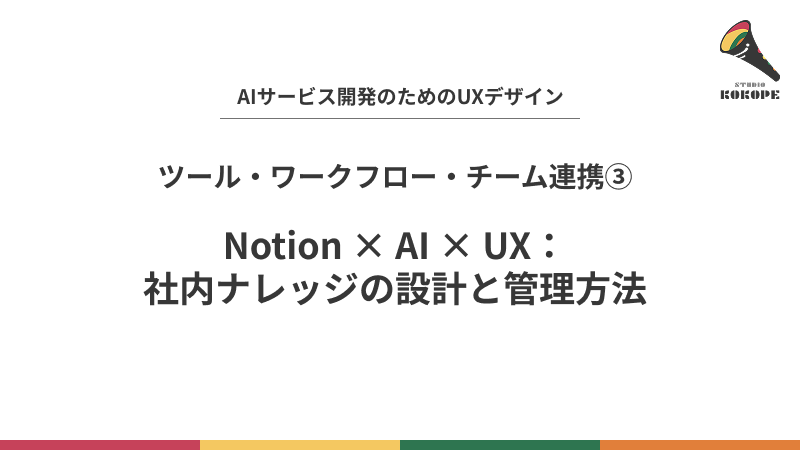
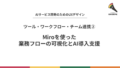
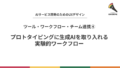
コメント