はじめに
AIエージェントやチャット型サービスを設計する際に、対話フローの設計は欠かせません。しかし、プロンプトの内容やシステムの返答パターンが複雑になればなるほど、チームでの共有やレビューが難しくなり、設計ミスや認識の齟齬につながることがあります。こうした問題を解決するために、Figmaを活用してAI対話フローを視覚化・共有するのは有効なアプローチです。
本記事では、Figmaで使えるAI対話フロー設計用テンプレートを紹介し、どのように対話体験を「見える化」し、チームで活用できるかについて述べてみます。
なぜFigmaで対話フローを可視化するのか?
FigmaはUI設計ツールとして知られていますが、近年は図解や情報設計のためのホワイトボードツールとしての用途も広がっています。対話設計においても、Figmaを使うことで以下のようなメリットがあります。
- チームでリアルタイムに対話構造を共有できる
- UIコンポーネントと会話の流れを同一ファイルで管理できる
- ステークホルダー(非エンジニア)にも説明しやすい
- プロトタイピングとの接続がスムーズ(対話フロー → UIモック)
つまり、UX・プロンプト設計・UI設計を一体で扱えるという利点があり、AIサービス開発におけるコラボレーションを加速させることができます。
テンプレートで設計する3つの要素
テンプレートは、以下の3つの要素を構造的に設計するために最適化されています。
1. ユーザー発話のバリエーション
- ユーザーが入力する可能性のある表現を複数記述(自然言語)
- タイプ別(質問・指示・迷い)に分類
- タグ付けして分類(例:業務用語、感情的、曖昧 など)
2. エージェントの返答タイプ
- 返答テンプレート(例:「かしこまりました」「それは少し難しいかもしれません」)
- モード切替の判断条件(例:「調子が悪いとき」→ 専門家呼び出し)
- 対話の分岐ポイント(ユーザーの選択肢や条件によるフロー分岐)
3. UIとの接続ポイント
- チャット画面上に表示されるメッセージの種類(固定 vs 動的)
- ボタンやドロップダウンなど、入力支援のUIパーツとの連携
- システム実行やAPI連携のタイミングを明示
実際のテンプレート構成(例)
テンプレートは以下のような構造になります。
- ページ1:対話設計マトリクス
縦軸に「ユーザーの入力タイプ」、横軸に「エージェントの反応タイプ」を並べた早見表 - ページ2:対話フローチャート(分岐型)
会話の起点から分岐を矢印で示すことで、パターンの網羅性を担保 - ページ3:UIモックとの接続図
対話フローの各ステップが、どのUI画面や操作に対応するかを視覚化 - ページ4:注釈+プロンプト設計用のフィールド
LLMへのプロンプト、システムの役割定義、制約条件などを記述可能に
Figmaのバリアント機能やAuto Layoutを活用して、柔軟かつ再利用可能な設計が可能です。
活用シーンと導入のポイント
活用シーン
- 新規AIエージェントサービスのゼロイチ設計
- 既存チャットボットの高度化
- ステークホルダー向け説明資料
- プロンプトエンジニアとの連携ドキュメント
導入時のポイント
- UIと分離しすぎず、密接に連携させること(体験の連続性を重視)
- 非デザイナーも編集できる設計にすること(フィールドや説明を工夫)
- 「現在どの対話にいるか」が把握しやすいナビゲーションを設けること
おわりに(まとめ)
AI対話のUXは、従来の画面設計以上に時間的・文脈的な流れを扱うものです。そのためには、画面の「見た目」だけでなく、会話の構造そのものを可視化するプロセスが欠かせません。
Figmaのテンプレートを使えば、複雑な会話設計もチームで共有・編集しながら進めることができます。UXデザイナーとしては、単なる画面の設計者ではなく、対話体験そのものの設計者として、AIとのコミュニケーションの質を支える存在になることが求められています。
今後さらに進化するAIエージェントの時代に向けて、「会話のデザイン」を形にする道具として、Figmaテンプレートの活用は大きな武器になるはずです。
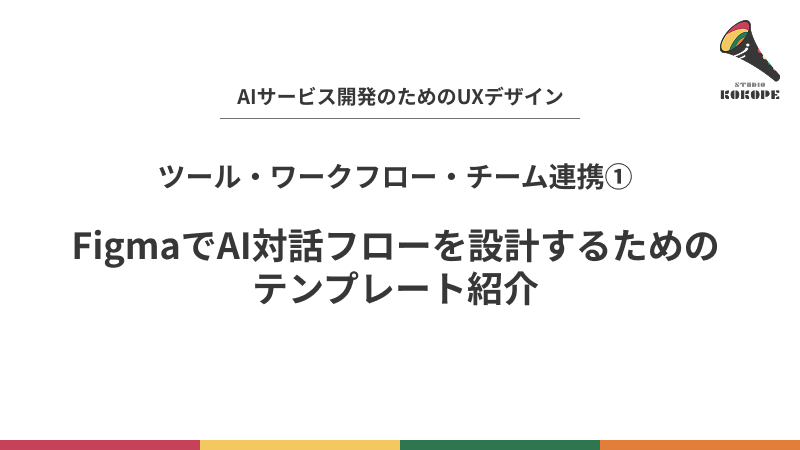
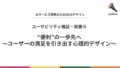
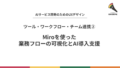
コメント