はじめに
色はプロトタイプでも重要な情報伝達手段──
UXデザインにおけるプロトタイピングは、ユーザー体験を検証する重要なステップです。ワイヤーフレームやモックアップの段階から色を適切に扱うことで、ユーザーやステークホルダーに意図を正しく伝えられます。
ただし、プロトタイプでの色選定は「美しく見せる」だけではなく、情報設計、心理的誘導、ブランドの一貫性を意識する必要があります。FigmaやMiroなどのツールを活用すると、デザインを効率的に検証・共有できるのも大きな利点です。
プロトタイプでの色設計のポイント
色の階層を明確にする
プロトタイプでは情報の優先度を色で示すことが有効です。
- メインアクション → 強調色で視線を誘導
- サブアクション → ブランドカラーの淡いトーンで補助的に表示
- 情報や背景 → ニュートラルカラーで安定感を演出
色の階層を明確にすることで、ユーザーは自然に重要な情報や操作を把握できます。
配色ルールをチームで統一する
プロトタイプは複数のデザイナーやステークホルダーが関わる場合が多く、色の統一性が崩れることがあります。
- デザインシステムにカラーガイドを用意
- Figmaでは「カラースタイル」を使って統一
- Miroではカラーパレットを事前に定義して共有
ルールを明確にすることで、作業効率とデザインの一貫性を両立できます。
Figmaでのカラー設計の工夫
カラースタイルの活用
Figmaでは「カラースタイル」を使うことで、ボタンやテキストなどに設定した色を一括管理できます。
- メリット
- ブランドカラーや階層色を統一
- カラー変更時に全体に反映される
- スタイル名をわかりやすくすることでチーム間共有が容易
コンポーネントへの適用
ボタンやカードなどのUIコンポーネントにカラースタイルを組み込むことで、変更や差し替えが容易になります。
- ボタンの状態(通常、ホバー、無効)ごとに色を定義
- UIコンポーネントを更新すると、全画面に反映
こうすることで、プロトタイプの精度と一貫性が向上します。
Miroでの色活用
ワークショップやアイデア整理での配色
Miroではブレインストーミングやカスタマージャーニーマップなどで色を使い分けることができます。
- 情報カテゴリごとに色分け → 直感的に整理
- 重要度や優先度を色で表現 → チーム内の視覚的合意を促す
- アクションや課題のタグ付け → 色で種類やステータスを明示
プロトタイプ検証の補助
Miro上で簡易的に画面案やフローを作り、色で強調することで、ユーザーやステークホルダーへの説明が容易になります。
色を扱う際の注意点
配色の一貫性と過剰装飾のバランス
- 強調色が多すぎる → ユーザーが情報の優先度を判断できない
- 色の階層が不明確 → 行動誘導が曖昧になる
- ブランドカラーを無理に全体に適用 → UXを損なう可能性
実際のユーザーで検証
プロトタイプで色を設定した後は、ユーザーテストでの確認が不可欠です。
- CTAやナビゲーションが色で直感的に理解できるか
- 情報の階層が色だけで認識されているか
- 色弱ユーザーにも配慮されているか
こうした検証で初めて、色の効果が確実にUXに反映されます。
おわりに(まとめ)
プロトタイピングにおける色設計は、単なる装飾ではなく、情報の整理・行動誘導・ブランド体験の統一に直結します。
- 色の階層を明確に → メイン/サブ/背景を整理
- カラースタイルやパレットで統一 → FigmaやMiroでの効率化
- 過剰装飾を避ける → UXの優先度を維持
- ユーザーテストで検証 → 認識の正確さと使いやすさを確認
色を意図的に設計し、チームで共有することで、プロトタイプの精度とUXの質を同時に高めることが可能です。プロトタイプ段階での色設計は、完成版のUXを成功させる重要な基盤となります。
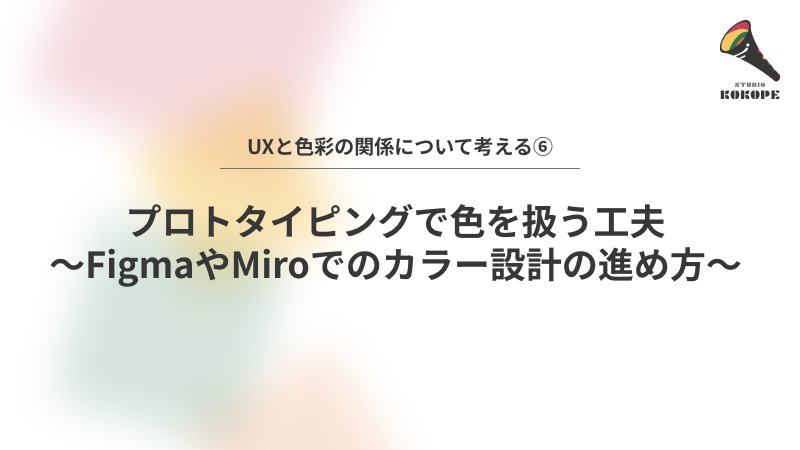
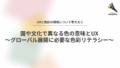
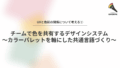
コメント