はじめに
AIサービスや業務自動化プロダクトの開発において、UXデザイナーがプロジェクト後半に呼ばれるというケースは今も多く見られます。「画面を作る段階になってから声がかかる」という状況では、根本的なユーザー課題の検討や、体験全体の設計が間に合わなくなってしまいます。
本記事では、UXが起点となるプロジェクト立ち上げの手法とマインドセットについて説明します。
UXが後追いになる理由とは?
まず、なぜUXが後追いになってしまうのでしょうか。その背景には以下のような要因があります。
- プロジェクトの初期が「技術」「ビジネス」起点で始まる
- UXが「UIを整える役割」と捉えられている
- デザイナー自身が早期フェーズでの関与を躊躇してしまう
このような構造のままでは、「できたものをユーザーに届ける」だけのUXにとどまってしまいます。それを変えるには、プロジェクトの種が生まれる段階からUXの視点を持ち込む必要があります。
UX起点でプロジェクトを立ち上げるメリット
UXを起点にすることで、以下のような好循環が生まれます。
- ユーザー視点で課題を構造化できる(技術よりも目的が明確になる)
- 仕様決定や要件定義がブレにくくなる
- 初期段階からリスクと可能性を可視化できる
特にAIや自動化領域では、「何ができるか」よりも「何に使われるべきか」を先に設計することが重要です。UXはその出発点となることができます。
UX起点のプロジェクト立ち上げステップ
ここでは、実践的なアプローチをステップごとに紹介します。
ステップ1:仮説の種を拾い、問いに変える
UXデザイナーは、プロダクトの「不確実な仮説」を構造化する力を持っています。以下のような問いを立て、関係者の発想を整理します。
- どんな業務上の課題を、誰が抱えているのか?
- なぜ今その課題に注目するのか?
- 現状のどのプロセスに「改善の余地」があるのか?
この段階ではFigmaよりもMiroやNotionを使い、構造化と共創に重きを置くのがポイントです。
ステップ2:ユーザー起点でアイデアを整理する
UX起点では、アイデアの出発点を「機能」ではなく「体験」に置きます。
- ジャーニーマップで業務の流れと課題を可視化
- ユースケースの優先度を比較・分類
- “これは誰にとってどう嬉しいのか?”を常に言語化
これにより、「技術的にできること」ではなく「意味のあること」にフォーカスした立ち上げが可能になります。
ステップ3:早期に動くプロトタイピングとフィードバック設計
Figmaで簡易なモックを作り、チーム内外でレビューを回すことで、
「立ち上げ中に既にフィードバックを得られている状態」が作れます。
- シナリオベースでプロトタイプを提示
- Notionに共有コメントを蓄積
- ユーザーインタビューを挟んで検証を早めに行う
このように、UX起点のプロジェクトでは“仮説検証”が自然に組み込まれた形になります。
UXが開発初期から関わるための環境づくり
UX起点の立ち上げを成功させるには、個人だけでなくチーム全体の理解や期待値調整も必要です。
- 「デザイナー=画面づくり」からの脱却をチームに促す
- 週次での進捗共有にUXの観点を持ち込む
- ビジネス・エンジニアサイドの意思決定プロセスに参加する
また、UX側から「こうすれば効果的に進められそうです」と提案をすることで、プロジェクトの推進役としての信頼を獲得することもできます。
おわりに(まとめ)
UXデザイナーが開発初期からプロジェクトに関わることで、より価値ある方向性をチーム全体に示すことが可能になります。「出てきたものを整える」のではなく、「最初の問いを設計する」ことでこそ、UXの本質的な力が発揮されます。不確実性が大きいAIサービス開発において、UX起点の立ち上げは、リスクを減らし、意味ある価値提供へとつながる確かなアプローチです。
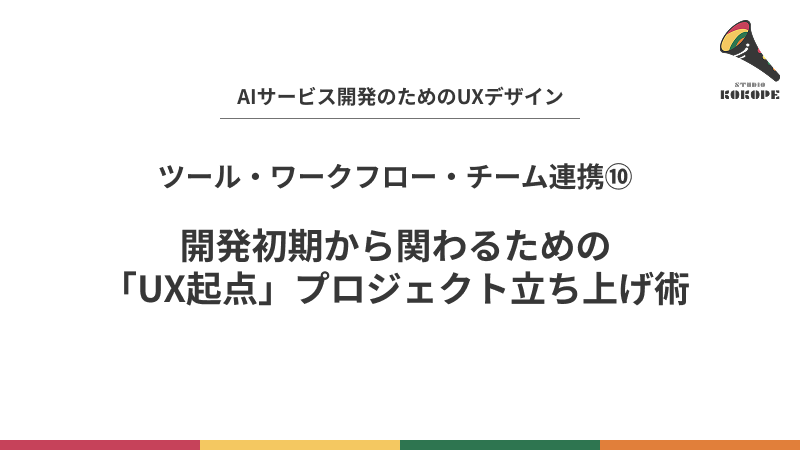
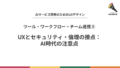
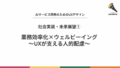
コメント