はじめに
生成AIや業務自動化ツールのようなプロダクトにおいて、UXデザインは非常に複雑な文脈を扱うことになります。特に、業務効率化やフロー改善を目指すサービスでは、「何をどうすれば便利になるのか」が表面的には見えづらいことが多く、ユーザー自身も気づいていない業務課題や、無意識の操作が存在するケースが少なくありません。だからこそ、UX改善を行う前提として欠かせないのが、業務理解=ユーザーの現場理解です。
この記事では、業務理解をどのように進め、どのようにUX改善に繋げていくのかを、現場との共創という視点から整理します。
なぜ業務理解がUX改善に不可欠なのか?
これは、表面的なUI改善では、本質的な課題は解決できないからです。たとえば、画面の情報量が多すぎて見づらい、ボタンの配置が悪くて使いにくいといった問題は、業務の全体像やプロセスを理解せずに改善しようとすると、かえって誤った最適化を生んでしまうことがあります。
実際にユーザーが置かれている業務の文脈を知らずに「直感的に使いやすいUI」を目指すと、現場の制約や優先度を無視した現実離れしたデザインになる危険もあるのです。
業務理解の第一歩:現場の声を“体験”する
業務理解とは、単に業務フローをヒアリングすることではありません。現場の体験を想像ではなく実感として捉えることが重要です。
具体的なアプローチとして、以下のような方法があります。
1. 業務フローの可視化
ユーザーが日常的に行っている操作、判断、確認作業を時系列・依存関係・頻度で整理します。
現場のホワイトボードやMiroなどを使って業務ジャーニーマップを共に描くことで、共通認識を育てます。
2. シャドーイング・同席観察
ユーザーの業務に実際に同席し、使っているツールや操作の流れを観察する。
表に出てこない裏技的な使い方や、ツールを跨ぐ工夫などは、このプロセスで初めて見えてきます。
3. 問題の“前後”を見る
今あるUIの問題点を聞くだけでなく、「その操作の前に何をしていたか」「後に何をするか」まで掘り下げます。
これにより、改善すべきポイントが単なるUIではなく、業務の連携部分にあることが分かることもあります。
共創の場を設計する:現場を巻き込む工夫
業務理解を深めるには、単なる取材対象ではなく「共にプロダクトを作るパートナー」として現場を巻き込む姿勢が重要です。
以下は、デザイナー主導で現場との共創を促進する工夫の例です。
- ワークショップ形式の改善会議
UIレビューではなく、「業務で困っていること」から始めて、課題を一緒に可視化する - プロトタイプを持ち込んで議論する
FigmaやMiroで作った簡単な画面イメージを元に、「これなら現場で使えるか?」をその場で確認 - フィードバックを「反映→報告」するサイクル
ユーザーの声を実装にどう活かしたかを可視化して、信頼と期待値の循環を作る
UX改善は「課題定義」の前で決まる
ユーザーの現場を知り、体験に触れ、感情に共感することは、UIを整える以前の話かもしれません。ですが、課題をどう定義するかこそがUXの最重要ポイントであり、業務理解が甘ければ、どんな優れたデザインも的外れになるリスクがあります。
現場との共創を通じて見えるのは、単なる操作の難しさではありません。現場の工夫、意図、優先度、そして妥協の跡といった、UXを設計する上で不可欠な「文脈のかけら」たちなのです。
おわりに(まとめ)
UX改善というと、どうしても「見た目」や「導線」など、ユーザーインターフェースの話に寄りがちです。しかし、本当に改善すべきは、UIの奥にある業務のリアルであり、それを知るには、現場との対話と共創が不可欠です。
UXデザイナーは、ユーザーの代弁者ではなく、ユーザーとともに課題を見つけ、言語化するパートナーであるべきであり、その第一歩は、改善提案をする前に、まずユーザーの日常に深く入り込むことにあります。
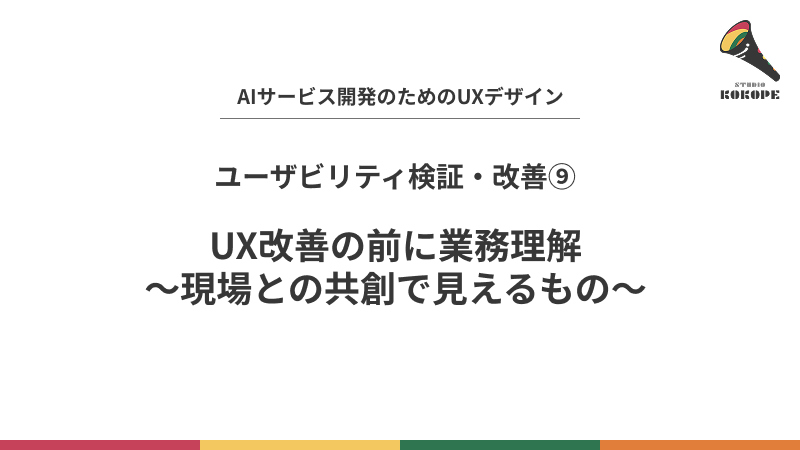
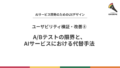
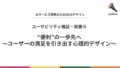
コメント