はじめに
AIエージェントや自動化ツールなどのプロダクトでは、ユーザーの行動を可視化するKPI(定量指標)が改善の指針として活用されることが多くなっています。たとえば「DAU」「完了率」「継続率」「自動化数」などは、チームの成果指標としても扱われます。しかし、こうした数値だけを見ていては、「なぜ使われたか/なぜ使われなかったか」という本質に気づけないこともあります。
特にUXデザイナーの視点では、数字では拾いきれない体験の質や感情、認識のズレといった定性的な情報が、改善の糸口となる場面が少なくありません。
本記事では、定性データからプロダクト改善を導く考え方と手法について述べています。
定性データとは何か?
定性データとは、数値ではなく「意味」や「背景」を含む情報を指します。ユーザーの発言、行動観察、チャットでの相談、フィードバックコメント、サポート履歴などが代表的な例です。たとえば以下のような情報は、KPIでは見えないインサイトを含んでいます。
- 「もっとシンプルだと思ってたけど、設定が複雑だった」
- 「なんとなく信頼できなくて、自動化を止めてしまった」
- 「思った通りの結果が出ない理由が分からない」
これらの声には、機能だけでなく体験の設計に対する評価が含まれており、UX改善に直結する材料となります。
なぜKPIだけでは不十分なのか?
KPIは「何が起きたか」を定量的に教えてくれますが、「なぜそれが起きたのか」までは教えてくれません。
たとえば:
- フローの完了率が下がっている → なぜ中断されたのか?
- エージェントの利用数が減った → どの時点で不安や不満があったのか?
- 再利用率が低下 → なぜ一度きりで離脱されたのか?
この「なぜ?」に答えるためには、ユーザーの言葉や行動の背景を丁寧に拾う必要があります。また、AIサービスのように、使い方に癖や試行錯誤が伴うプロダクトでは、定量的な指標だけでは成功や失敗の本質を掴みづらいという性質があります。
定性データを活かしたUX改善アプローチ
UXデザイナーが実践できる、定性データに基づいた改善アプローチをいくつか紹介します。
1. ユーザーインタビューや声の「構造化」
ただ話を聞くだけでなく、発言を利用フェーズ別(初期・設定・実行・結果確認)や感情軸(困惑・納得・感動)で整理することで、どこに課題があるかが見えてきます。
2. ユーザビリティテストの記録活用
ユーザーが迷った場所、クリックを躊躇した箇所、質問が集中したタイミングなどを記録し、定量のログと突き合わせて仮説検証に活用します。
3. フィードバックの収集と分類
サポートチャット、フォーム、アンケートで集まった定性的なフィードバックを**タグ分け(例:不安・混乱・期待とのギャップ)**し、共通傾向を洗い出します。
4. カスタマージャーニーマップとの照合
既存のCJマップに定性データをマッピングし、想定した感情と実際の声のズレを可視化することで、設計意図の調整が可能になります。
定性データを活かすためのチーム内共有術
定性データは抽象度が高いため、チームに共有しても「主観的だ」と受け止められやすい側面があります。そのため、以下のような方法で共通言語化・可視化していくことが重要です。
- 抜粋+カテゴリ分けされた声をMiroなどで共有
- 実際の発話やチャットログのスクショで「生の声」を伝える
- インサイトごとの「仮説ラベル」を用意して、検証ステップとセットで示す
- 定性のインサイトをKPI改善の根拠として紐づける(例:「◯◯の設定率が低いのは、この発言と一致する」など)
UXデザイナーとしての言語化・図解能力が、ここで大きな役割を果たします。
おわりに(まとめ)
数字は強力な指標ですが、数字が語らないことに耳を傾けることが、UXの改善には欠かせません。特に、AIエージェントのように、使い手の理解や感情が体験を大きく左右するプロダクトでは、「なぜ、そう感じたのか?」を掘り下げる定性アプローチが価値を発揮します。よって、定量と定性、両者を組み合わせることで、プロダクトの「見えている部分」と「見えていない部分」の両方にアプローチできるようになります。
UXデザイナーは、目に見えないものを言語化し、設計に落とし込む存在です。声なき声を拾い、数字の裏側を読み解くこともまた、私たちにしかできない仕事のひとつだと言えるでしょう。
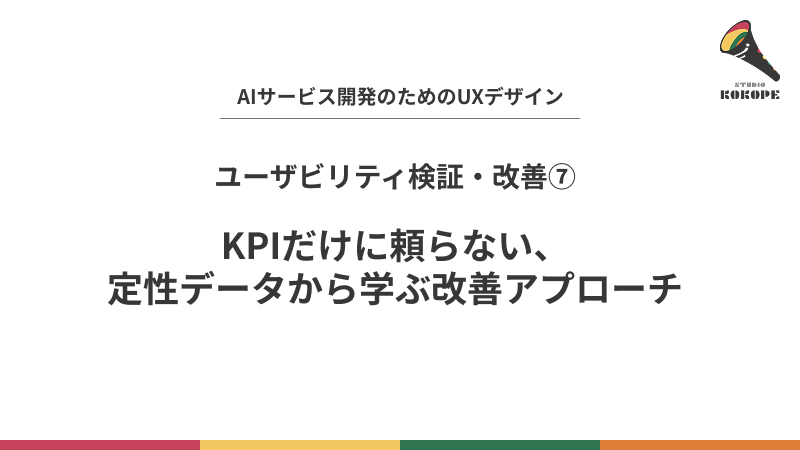
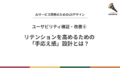
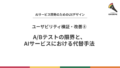
コメント