はじめに
AIエージェントは便利で柔軟な存在ですが、どれほど高精度であっても間違えることがあります。出力が意図にそぐわない、不正確な情報を含む、行動が止まってしまう、思い通りに動作しない――。こうした“AIのエラー”に直面したとき、ユーザーの信頼をつなぎとめるのがエラーハンドリングのUX設計です。従来のシステムエラーとは異なり、生成AIやエージェントにおける失敗は、不確実性や期待とのズレとして現れます。
本記事では、AIエージェントにおけるエラーハンドリングの種類とUXの考え方、ユーザーにとって納得感のある設計について掘り下げます。
AIエージェントにおける「エラー」とは何か?
AIエージェントが起こすエラーは、大きく分けて以下の3つに分類できます。
1. 事実誤認(ハルシネーション)
事実に反する情報を自信満々に提示するケースです。
例:「2025年のオリンピックは大阪で開催されます」など、実在しない情報を提示する。
2. 期待とのズレ
ユーザーが期待していた出力や動作と、実際の挙動が異なるケースです。
例:書類要約を依頼したのに単なる抜き書きになっているなど。
3. タスク失敗・途中停止
AIが指示されたタスクを完了できず、途中で止まったり、エラーを返したりするケースです。外部API連携の失敗や、ステップ実行中の処理エラーなどもここに含まれます。
これらはいずれも、「AIが間違えた」とユーザーに思わせる体験であり、心理的インパクトは大きくなります。だからこそ、単に「エラーメッセージを出す」だけでは不十分です。
UXとしてのエラーハンドリングの基本姿勢
AIサービスにおけるエラーハンドリングは、以下の3つの視点が重要です。
1. 驚かせないこと
突然、意図しない結果が表示されると、ユーザーは混乱し、AIへの信頼を一気に失ってしまいます。たとえエラーが不可避であっても、「なぜそうなったか」をわかりやすく伝えることで、安心感を維持できます。
2. 責任の所在を曖昧にしないこと
「申し訳ありません」「処理できませんでした」などのメッセージは、AI側が失敗したことを明確に認める必要があります。あいまいな表現やユーザーのせいにするような言い回しは避けるべきです。
3. 次の行動につなげること
エラーのあとに「どうすればいいか」が示されないと、ユーザーは離脱してしまいます。リトライ、編集、問い合わせなど、回復手段をUI上でガイドすることが必須です。
ケース別:エラーハンドリングの設計パターン
パターン1:ハルシネーションの可能性がある場合
- 補足テキスト:「この情報はAIによって生成されました。必ずご自身でご確認ください」
- 出力に出典表示や引用リンクを添える(RAGと併用)
- 検証可能な情報は明示的に区別する(例:数字・日時・統計)
パターン2:期待と異なる出力になった場合
- 「こういった意図ではありませんか?」と追加選択肢を提示する
- 出力後に「再生成」「編集」などのアクションをすぐ用意する
- 目的別テンプレートの活用で初期プロンプトの精度を高める
パターン3:タスクが途中で失敗した場合
- どのステップでエラーが発生したかを明示する
- システムエラーは開発チーム向けに詳細ログを保存しつつ、ユーザー向けには簡易な説明にとどめる
- 「後で再試行」「他の方法を試す」などの代替案を用意する
エラー体験を「納得感」に変えるためのUI工夫
ユーザーがエラーを受け入れるかどうかは、納得感があるかどうかにかかっています。そのために、次のような工夫が有効です。
- 事前にAIの限界を伝える:「このエージェントは資料整理を補助しますが、正確な要約は保証されません」などの文言を設計段階で入れる。
- 原因を“対話的”に伝える:「契約書のPDFを解析できませんでした。パスワードがかかっていないかご確認ください」など、具体性のある説明を心がける。
- ユーザー側の対処が明確である:「〇〇を再アップロードしてください」「内容を短くして再度お試しください」といった、次の一手を示す。
おわりに(まとめ)
AIエージェントは万能ではありません。間違えること、期待を裏切ることもあるのが前提です。だからこそ、その瞬間の体験設計が、プロダクトの信頼性を左右します。
エラーとは単なる障害ではなく、ユーザーとAIとのコミュニケーションの一部です。UXデザイナーは、技術の限界を隠すのではなく、どのように伝え、どのように導くかを設計する役割を担っています。
プロダクトが「失敗から逃げない設計」になっているかどうか。それが、AI時代のUXにおける新しい評価軸となっていくでしょう。
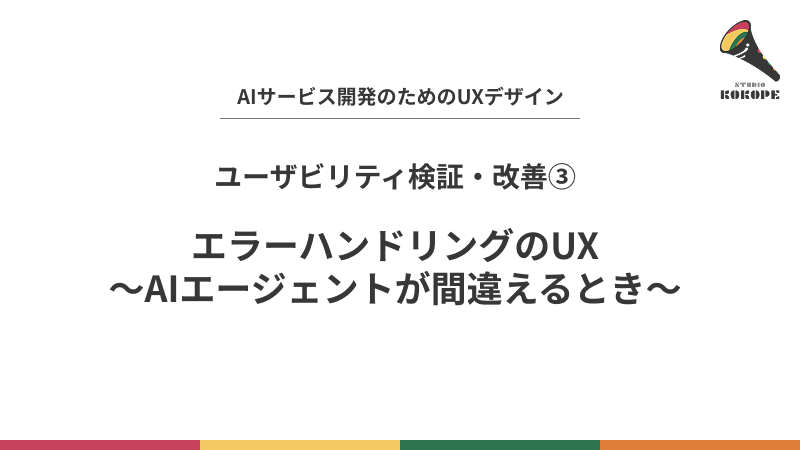
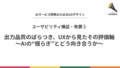
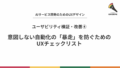
コメント