はじめに
AIエージェントが提供する回答に対して、ユーザーは常に「それ、ホント?」「なぜそう言えるの?」という疑念を抱く可能性があります。特に、業務用途や意思決定に関わるような文脈では、この「信頼感の構築」がプロダクトの生命線となります。
こうした背景で注目されている技術が、RAG(検索拡張生成:Retrieval-Augmented Generation)。AIが回答を生成する際に、ナレッジベースや外部ドキュメントから関連情報を検索・参照し、その内容に基づいて出力を行う仕組みです。
本記事では、RAGを活用したAIエージェントにおける「情報ソース提示のUX」に焦点を当て、どのように見せ方・構造を設計すべきかを考察します。
なぜRAG型AIには“出典のUX”が必要なのか?
ユーザーの不信感を和らげる
→ 出典が明示されていないAIの回答は「なぜそう言えるのか」がブラックボックス化しがち。
ユーザーが「自分で判断」できる材料を提供する
→ 特に意思決定において、裏付け情報があれば判断が早く、納得も深くなる。
フィードバックループを作れる
→ 間違いや誤解があっても、「このソースが原因かも」とユーザーが気付ける。
RAG型出力でありがちなUXの失敗
- 出典リンクが羅列されているだけで、どこにどう使われたか不明
- 参考文献が多すぎて逆に混乱
- 情報ソースが専門的すぎて読解できない
- 「それっぽく見える」だけで、実際には文脈と合っていない
このような設計ミスがあると、せっかくのRAGの効果も“ノイズ”となってしまいます。
良質なRAG体験を支えるUX設計のポイント
パターン1|出典を「インライン」で示す
- 回答内の文末や単語横に小さく [1], [2] のような参照リンク
- ユーザーが「この文はどのソースに基づいているか」が直感的に分かる
- 例:「この商品は2019年から出荷が停止されています」
パターン2|ソースの「要約」や「見出し化」
- 原文ではなく、ポイントだけ抜き出して提示
- クリック前に「読む価値があるか」が分かる
- 例:「この出典では、Aという理由で対応策Bを提案しています」
パターン3|回答とソースの「対応関係」を明示
- 回答の各段落と、それを支える情報の抜粋・リンクをセットで表示
- 情報の信頼性と、回答の構成理解を両立できる
パターン4|出典情報の種類や信頼度を可視化
- 社内文書/公開資料/FAQ/Slackログ など、ソースタイプをアイコンや色で示す
- 「この情報は公式資料に基づいています」などの補足ラベル
パターン5|全文表示・ドリルダウンのしやすさ
- 出典をその場で展開・全文表示可能にする
- 「もっと詳しく知りたい」にすぐ応えられる体験設計
デザイナーが押さえておくべき観点
| UX観点 | なぜ重要か | 工夫例 |
|---|---|---|
| 読みやすさ | 情報が長すぎると離脱される | 要約、折りたたみ、見出し強調 |
| 信頼性の視覚化 | 出典の重要度を視覚的に伝える | ラベル・信頼度バー・アイコン |
| 情報の関連度 | 「その情報がどう使われたか」が分かる | インライン表示、段落対応表示 |
| 文脈の保護 | ソースの“誤用”を防ぐ | 元文への遷移、元文の周辺文脈も表示 |
実例:情報ソース提示のUXパターン比較
| サービス | ソース提示の特徴 | UX評価 |
|---|---|---|
| Perplexity AI | 段落ごとにソース分離・インラインリンクあり | ◎ 信頼感高・操作直感的 |
| ChatGPT(RAGカスタム) | 回答下部にまとめてリンク列挙 | △ 利用者によっては“気づかない”可能性 |
| Dify(LLM UI) | 検索→参照→生成の3ステップ明示 | ○ 意図は明確だが、冗長になりがち |
おわりに(まとめ)
RAG型のAIエージェントは、「生成される情報の正しさ」だけでなく、「その根拠をどうユーザーに伝えるか」によって、体験の価値が大きく左右されます。これは、まさに情報設計=インフォメーションアーキテクチャであり、UXデザイナーの存在感を示せる領域と言えます。
- ソースをどうまとめるか
- どう読みやすく、納得感を持たせるか
- どうユーザーが自信を持って活用できるか
RAGの精度向上だけでなく、UXによる「意味の伝わりやすさ」を両輪で高めていくことが、信頼されるAIプロダクトへの第一歩になるでしょう。
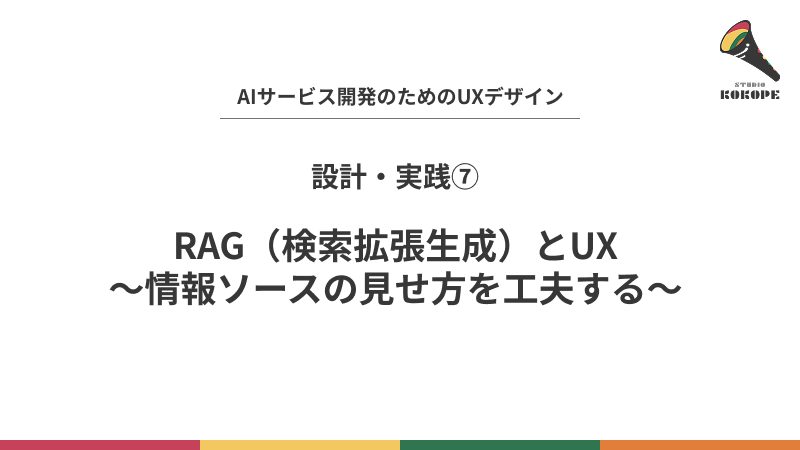
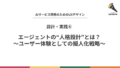
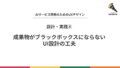
コメント