はじめに
「このAI、なんか信用できない」
「何ができるか、正直よく分からなかった」
AIプロダクトのユーザー調査を行っていると、従来のSaaSやWebアプリではあまり出てこなかった”感情”や”印象”のズレが現れてきます。
従来のリサーチでは「使いやすいか」「分かりやすいか」「求めている機能があるか」に焦点が当たっていましたが、生成AIプロダクトでは、それだけでは不十分です。なぜなら、AIの出力には“揺らぎ”があり、「信頼してもいいのか」「任せて大丈夫か」といった感情的な判断がUXの鍵を握るからです。
この記事では、UXデザイナーの立場から「AIプロダクトにおけるユーザーリサーチの焦点」について、従来との違いを踏まえながら解説します。
通常のプロダクトリサーチとAIリサーチの違い
| 観点 | 従来のUI/UXリサーチ | AIプロダクトのリサーチ |
|---|---|---|
| 正解の有無 | ユーザーの期待と一致すれば正解がある | 出力に正解がない/揺らぐことが前提 |
| インタラクション | 明示的な操作(クリック・選択など) | 対話やプロンプトによるあいまいな入力 |
| エラーの扱い | システム側の不備として扱われる | 許容される“間違い”と“納得できない”の境界が曖昧 |
| 満足度の構成要素 | 機能性・速度・デザインなど | 信頼感・透明性・コントロール感が重要な指標に加わる |
ユーザーリサーチで焦点を当てるべき5つの観点
1. 期待の持ち方(メンタルモデル)
- ユーザーが「どのような存在」としてAIを認識しているか?(秘書?アシスタント?チャット窓?)
- 機能への期待値が高すぎたり、逆に信用されていなかったりする場合がある
質問例:
「このAIは何をしてくれると思いましたか?」
「“間違ったとき”に、どう感じましたか?」
2. 理解度(透明性と説明可能性)
- 出力の根拠が不明なときに不安を感じていないか?
- UI上でどこまでの文脈・意図が伝わっているか?
質問例:
「この回答の元になった情報があるとしたら、見たいですか?」
「なぜこの答えが返ってきたと思いますか?」
3. コントロール感(任せる vs 操作する)
- AIが勝手に動くことで「楽」だと感じているか、「怖い」と感じているか?
- ユーザーが結果に対して“納得感”を持てる構造になっているか?
質問例:
「この作業はAIに任せたいと思いましたか?なぜ?」
「自分で選択できた方が安心ですか?」
4. 信頼構築の瞬間(いつ、どの行動で)
- どの瞬間に「このAI、使えそう」と感じたか?
- 小さな成功体験や一貫した応答が信頼の形成につながっているか?
質問例:
「“これは良かった”と思えた瞬間はありましたか?」
「どういう応答だったら、信頼できますか?」
5. 誤答・曖昧さへの許容範囲
- 明らかに間違っていても“役に立つ”と感じるケースは?
- ユーザーがAIにどこまでの正確さ・厳密さを求めているか?
質問例:
「この回答が間違っていたとしても、どの程度なら許容できますか?」
「この間違いが“困るケース”って、どんな場面ですか?」
リサーチ設計の工夫:AIならではのアプローチ
出力の「ばらつき」を評価に活かす
同じ入力でも出力が揺れるAIでは、「そのばらつきが体験にどう影響するか」を見ることが重要。
→ 複数パターンを見せて反応を聞く「変動型テスト」も有効です。
ユースケースを「タスク」ではなく「問い」で設計
「〇〇をしてください」ではなく、「〇〇について知りたいとき、どうしますか?」のように、動機ベースでリサーチシナリオを組むと、AIとのインタラクションが自然になります。
UIだけでなく、「返答の語調」や「返信スピード」に対する印象もヒアリング
→ トーンや演出も体験の一部と捉え、パーソナリティ設計に活かす
おわりに(まとめ)
生成AIがプロダクトに組み込まれる時代において、UXリサーチもまた進化が求められています。AIは人間と違って「正解をくれる存在」ではありません。その中で私たちが探るべきは、「どんなときに人はAIを頼れるか」「どんなふるまいに信頼を感じるか」という“信頼体験”の設計です。
UXデザイナーとしてリサーチを行うときには、以下の3つの視点を意識しましょう。
- ユーザーの期待や理解と、AIの挙動とのギャップを探る
- コントロール感・説明性・感情反応に注目する
- “使えるかどうか”より、“任せられるかどうか”を測る
この視点こそが、AI時代のUXを前進させるヒントになるはずです。
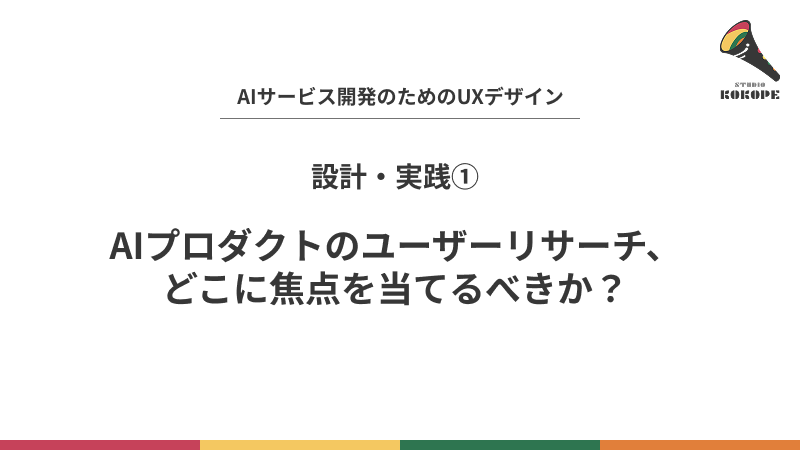
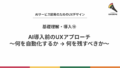
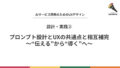
コメント