はじめに
「どこにAIを導入するか」より前に、「業務のどこがどうなっているのか」を知っていますか?
生成AIや業務自動化ツールの導入が現実的な選択肢になってきた今、「この業務、AIで自動化できませんか?」という相談を受ける機会が私自身も増えてきました。
でも、実際にプロジェクトに入ってみるとこう感じます。
- 誰がどのように業務を進めているかが見えていない
- 業務が属人化していて、人によって手順や認識が違う
- AIで解決する前に、人間の整理が必要な状態になっている
こうした状況に対して、UXデザイナーが持ち込める最大の価値は、業務の構造を「見える化」し、共通認識をつくることです。それが、本当に有効なAI導入の第一歩になります。
なぜ業務プロセスの可視化が必要なのか?
「自動化できる」より、「していいのか」の判断材料になる
AIで自動化できる業務は増えています。しかし、すべての業務を機械に任せるべきではないはずです。
- 判断が曖昧で文脈依存な業務
- 顧客との関係構築が求められる場面
- チームメンバー同士の信頼感をつくる“ちょっとした確認”など
これらは効率化の対象ではなく、むしろ「人間らしさを残すべき業務」かもしれません。それを見極めるには、業務の構造と感情の流れを理解することが不可欠です。
UX観点での「業務プロセス可視化」アプローチ
Step 1:現場ヒアリングで「実態」をつかむ
まずやるべきは、現場の人の「実際の業務の進め方」を聞くこと。マニュアルではなく、「いつ、誰と、何を見て、どう判断しているか」を引き出します。
- ユーザーインタビューの要領でヒアリングする
- タッチポイント、感情の起伏、迷いポイントなども把握する
- 表現できるなら、「フリクションマップ」を作ると効果的
Step 2:業務フローを図解化(As-Is)
ヒアリング内容をもとに、現状の業務プロセスを可視化します。Miro、Whimsical、FigJamなどが有効です。図解には以下の要素を含めるとより有用です。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| タスクステップ | 業務の流れ(誰が、何を、いつ) |
| 使用ツール | 使用中のSaaS・エクセル・手作業など |
| 感情 | 面倒くさい/確認が多い/心理的ストレスなど |
| 属人性 | 特定の人しか判断できない場面の可視化 |
| “非効率だが必要”な業務 | 気配り・合意形成・再確認 など |
Step 3:AI導入の仮説マッピング(To-Be)
ここまで整理した業務フローの中で、以下の視点からAIが補完できるポイントを洗い出します。
- 書き換え・コピペ・分類など、繰り返しが多い作業
- 複数の情報を集約し要約・変換するような情報整理業務
- 社内FAQ、申請処理など、パターン化されている対応
- メール・チャットでの文書作成支援・文章トーンの整形
ここで重要なのは、「自動化できそうな箇所を探すこと」ではなく、「AIが関わることで体験がよくなる箇所」を見極めることです。
可視化によって得られる3つの効果
1. チーム内の認識がそろう
「その業務って誰がどうやってるの?」という不明点が解消され、部署を超えた共通認識がつくれます。
2. AI導入の「納得感」が生まれる
可視化されたプロセス上にAIが「どう関わるか」が明示されることで、関係者の不安や拒否感を軽減できます。
3. 改善サイクルが回しやすくなる
後から振り返ったときも、「どこを、なぜ変えたか」が説明できるため、継続的な改善やフィードバックの基盤になります。
おわりに(まとめ)
AI導入=機能追加ではありません。人の仕事の一部を「任せる」という意思決定であり、その判断は現場理解と設計力がなければ難しいものです。
UXデザイナーは、その導入プロセスにおいて、
- 情報を構造化し
- チームの視界をそろえ
- AIを“適切に置く”ための土台をつくる
という、まさに「設計」の本質に関わる役割を担っています。
ノーコードやLLMの進化に目を奪われがちな今こそ、「どこにAIを置くべきか」以前に「何を残すべきか」を考えるUX視点が求められています。
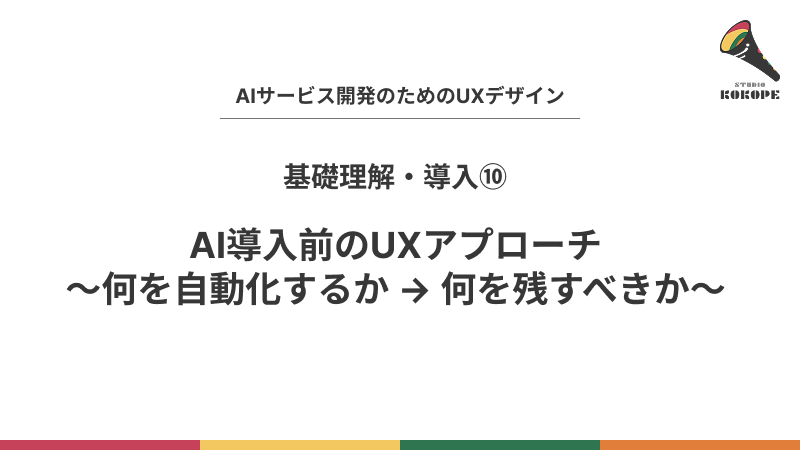
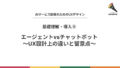
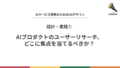
コメント