はじめに
「AIチャット機能を追加したいんだけど、エージェントでいける?」そんな会話、プロジェクトの初期に耳にしたことはありませんか?
「エージェント」と「チャットボット」は似たような存在に見えて、実はその体験構造・設計思想・役割の違いは大きく異なります。
本記事では、UXデザイナーの視点から両者の違いを分かりやすく整理し、どんなときにどちらを選ぶべきか、設計上の留意点は何かを解説していきます。
「チャットボット」と「エージェント」の基本定義
まずはざっくりとした定義から整理しておきます。
| 区分 | チャットボット | エージェント |
|---|---|---|
| 主な役割 | 決まった質問に答える、情報を返す | 目標達成のために自律的に判断し、実行する |
| 対話の構造 | 単発的なやり取りが中心(Q&A型) | 状態を記憶し、複数ステップにまたがる対話が可能 |
| 制御ロジック | シナリオベース(if-then) | LLM+外部ツール連携(RAG、ツール呼び出しなど) |
| UIの中心 | 会話ウィンドウ | 会話+アクションUI+状態フィードバック |
ユーザー体験の違いを設計視点で比較すると?
UXデザインでは、「見た目」よりも「期待される行動と体験」の違いが重要です。以下のような観点で設計ポイントが変わってきます。
目的の違い:質問回答 vs 目的達成
- チャットボットは「今この情報を知りたい」というニーズに即答するもの。
- エージェントは「目的を果たす」ことにコミットする。
→「すぐ知りたい」ならチャットボット。「一連の作業をサポートしてほしい」ならエージェント。
判断の違い:決められた道 vs 自分で考える
- チャットボットはスクリプト通りに進む。分岐は制作者が設計したものだけ。
- エージェントは入力を解釈し、状況に応じて手順や対応を“柔軟に”選ぶ。
→「判断をあらかじめ決める設計」と、「判断させるための条件設計」ではUXの責任範囲が違う。
体験の持続性:1回きり vs 継続的な関係性
- チャットボットは、会話が終われば完結(基本は無記憶)
- エージェントは、文脈・履歴・目的を保持して進行できる
→「何度も使う」前提なら、継続性あるUX(記憶・設定の保持・履歴表示)を持たせるべき。
UI設計における注意点
チャットボットでの注意点(FAQ対応など)
- 誤解が生まれないような選択肢設計が重要(入力自由度を下げてUXを安定化)
- 言葉の言い換え(パラフレーズ)を丁寧に設計することで認識精度を高められる
- 「この内容は役に立ちましたか?」のようなユーザー評価UIを用意して改善ループを回す
エージェントでの注意点(業務自動化アシスタントなど)
- 処理の進捗が可視化されていないと不安になるため、状態管理UI(ステータス表示)が重要
- ユーザーの主導権を奪わない設計(提案→選択→実行の順で進める構造など)
- 「説明可能性(Why)」を意識した出力設計が、AIへの信頼に直結する
プロジェクト選定時にチェックすべきポイント
以下のような問いを使うと、「チャットボットにするか」「エージェントにするか」の判断が明確になります。
- ユーザーの目的は、情報を得ること?行動を起こすこと?
- 会話の中で「手を動かす処理」は必要?(予約、分類、登録など)
- タスク完了までに複数の工程や条件分岐がある?
- 「この先どうなる?」という不安にどう答える?
このような観点で整理し、技術だけでなく「体験全体」を考慮して選定するのがUXデザイナーの役割です。
おわりに(まとめ)
「チャットで会話するUI」という表面的な共通点に惑わされることなく、「ユーザーが求めているのは「返事」か「行動」か?」という本質を見極めることが大切です。
UXデザイナーとしては、次のような設計のスタンスが求められます。
- チャットボット=会話を支援するUX
- エージェント=目標達成を支援するUX
いずれにしても、AIの進化がユーザー体験の期待値を引き上げている今、私たちは「動く」「賢い」だけではない、「安心できる、任せられる体験」をデザインしていく必要があります。
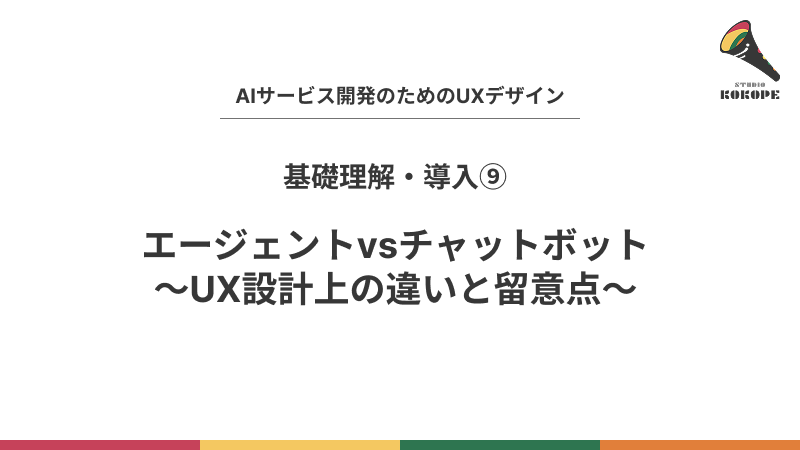
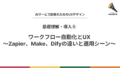
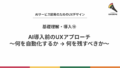
コメント