はじめに
自動化は、「動いた」だけでは不十分。
それが「どう体験されるか」まで設計するのがUXデザイナーの仕事です。
業務効率化やAI活用が求められる中で、ノーコードの自動化ツールを使っ「業務フローの構築」が日常的になりつつあります。特に私たちUXデザイナーも、FigmaだけではなくZapierやMake、Difyのようなツールに触れる機会が増えてきました。
でも、こういったツールの違いを「UXの観点から語る」場はまだ少ないのが現状です。
この記事では、Zapier / Make / Difyという代表的な3つのツールを比較しながら、UX設計者がどう向き合えば良いのか、どんな視点で選定すべきかを解説します。
なぜUX視点でのツール選定が重要なのか?
同じような「タスク自動化ツール」でも、以下のような違いがあります。
- タスクの構造や状態が見えるかどうか
- 複雑な分岐や再実行がやりやすいか
- ユーザーが今なにが起きているか分かるか
つまり、技術的には同じようなことができても、「どう体験されるか」には大きな差があるのです。そしてそれは、導入後のトラブル率、使い続けられるかどうかに直結します。
3大ツールの特徴とUX観点からの比較
以下に、Zapier / Make / Dify の特徴を整理した比較表を掲載します。実務で使ってきた体感をベースに、UX的な視点に絞ってまとめました。
| ツール | 概要 | UX的に優れている点 | 注意すべき点 | 適しているシーン |
|---|---|---|---|---|
| Zapier | シンプルなIFTTT型自動化。UIも直感的 | 導線が明快。失敗時の通知が分かりやすい | 条件分岐や複雑な構成が苦手 | 単純なSlack通知、Googleフォーム連携などの軽量自動化 |
| Make(旧Integromat) | ビジュアル型のフロー自動化。複雑な処理が得意 | 流れ全体が「見える」。誰でも構造を把握できる | 初見のUIがやや取っつきづらい | 分岐・ループ・集計などを含む複雑な業務プロセス |
| Dify | LLMを中核にしたAIエージェント構築ツール | 対話フローやプロンプト設計に特化。UIとAIが融合 | 「自動化」というより「体験づくり」に寄っている | AIを介した業務アシスタントや対話型プロダクトの設計 |
UX設計で考えるべきツール選定のポイント
ユーザーは今「何が起きているか」分かるか?
- Zapierはログが時系列で整理されていて、失敗に気づきやすい
- Makeはビジュアルで全体を把握しやすく、複雑さに対応しやすい
→ 運用者が属人化せず、誰でも保守しやすい体験に繋がる
自動化された「裏側」が、ユーザーにどう伝わるか?
- DifyではAIが判断・提案してくれるが、その意図が説明されないと不安になる
- Makeで組んだ自動化も、ユーザーに「ちゃんと動いた」と伝える設計がないと混乱する
→ フィードバック設計もUXデザイナーの重要な役割
例外処理・エラー時の体験をどうするか?
- Zapierは失敗時にアラートを送ってくれるが、その後のフロー設計はユーザー任せ
- Makeは柔軟な再処理ルールを組めるが、設計ミスがあると動かないままになる
→ 「止まらない仕組み」と「復旧できる導線」の両方を設計する必要あり
実際にどんな場面で使い分けるべきか?
Zapier を使うべき場面
- Googleフォーム入力 → Slack通知 → Googleスプレッドシート保存 のような単純な1対1フロー
- 複雑な判断を必要としない、即導入向き
Make を使うべき場面
- ユーザーが送信した複数のデータを条件ごとに処理し、複数の担当者へルート分岐させる、などの複雑な業務自動化
- フロー構成が増えていく前提のPoC設計や社内向け運用
Dify を使うべき場面
- 顧客対応ログをもとに「要約・分類・回答案」を生成するAIアシスタント
- 社内ナレッジ検索をチャットUIで提供し、ユーザーが対話しながら情報にアクセスできる設計など
おわりに(まとめ)
ツール選びはUX設計そのものです。動けばいい、早ければいい、ではなく、「チームが使い続けられる」「ユーザーが混乱しない」「改善しやすい」という観点で選ぶ必要があります。そして、その判断ができるのは、技術だけでなく体験全体を俯瞰できるUXデザイナーです。
ノーコードツールが民主化された今だからこそ、デザインの力で「無理なく使える仕組み」を設計することが、私たちの新しい役割だと思います。
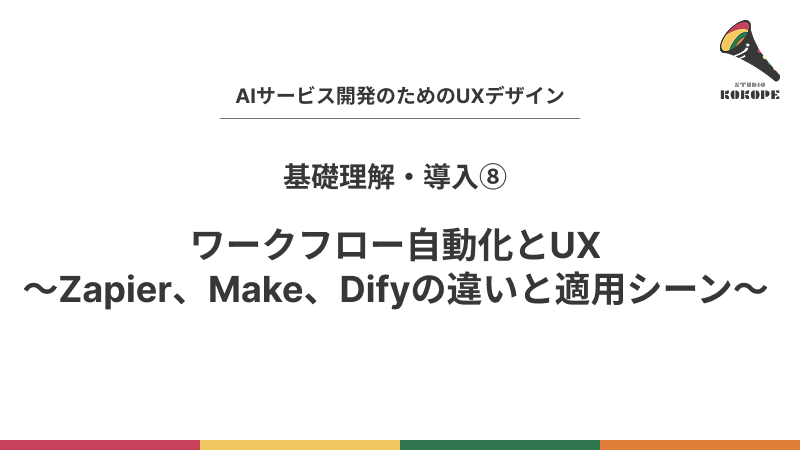
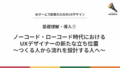
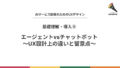
コメント