デザインチーム発足時や日頃のコミュニケーションにおいて、いろいろな課題があるが、支援・変革思考の強い私の場合の関係構築のコツをまとめてみる。
1. 「ゆるい接点」を作る(情報共有のハードルを下げる)
タスクが分かれていると、会話の必然性が減り、情報も閉じてしまいがちになる。そこでまずは「雑談以上、会議未満」の接点を意図的に作ることが重要である。
週1回・30分だけの「デザインシェア会」
→ 形式ばらなくてもOK。「最近気づいたこと」「作ってみたけど悩んだUI」「面白い記事」など、なんでも話す場にする。
「雑談チャンネル」や「#スクショ報告」Slackチャンネル
→ 完成してなくても良いから、Figmaの途中経過をポンと貼るだけの文化を促す。
👉こうした小さな接点が、信頼関係や「他の人のやり方を知る」きっかけになる。
2. 「暗黙知」を軽く言語化してみる
やり方の違いや思考のばらつきがあるなら、それを責めずに「見える化」してみるのが一つの手である。
- 自分のタスクを進めるときの「プロセスや判断ポイント」を図解または文章で共有
- 「なぜこうデザインしたのか?」を軽く言葉にしてまとめておく
- よくある作業の手順やFigmaの使い方をテンプレート化する
👉これは「統一するため」ではなく、互いの違いを理解する土台づくりとして行うのがポイント
3. 「1on1やペア作業」の導入も検討
少人数チームでは、あえて一時的に誰かと作業を一緒にする場を作ることで、思考の共有やスキル伝播が生まれる。
- 隔週で「ペアデザインタイム」を設ける(1時間だけでもOK)
- お互いの作業を「画面共有しながら見る会」
- ちょっとした1on1で「どうやってデザインしてるか」話してみる
👉プレッシャーにならないカジュアルな形が良い。目的は仕事の進行ではなく、関係性づくりとお互いの理解である。
4. 最初の「デザイン共通資産」を作ってみる
文化やスタイルが定まっていないなら、最初の一歩として小さな共通資産を作ってみる。
- Figmaの「共通スタイルガイド」(色・文字・余白などの最小セット)
- UIコンポーネントの「パーツライブラリ」第一弾
- 「レビューのときに見ておきたいポイント」のチェックリスト
👉一人で全部やらず、「これはチームで育てる資産です」と提案し、巻き込み型にすることで、チーム意識も高まっていく。
5. 焦らず、「文化を育てる人」として関わる
急にまとまることを期待しなくてOK。立ち上げ期は「混沌→試行錯誤→文化醸成」という時間の流れが必ずある。今できることは、
- 自分から1つ仕組みを提案してみる
- たまに会話を始めてみる
- 互いのやり方を尊重しつつ「共通点」を探る
👉これを無理なく継続できる形で取り組んでいけば、数ヶ月後には必ず変化が見えてくる。
人間関係がうまくいかないとき
実際、どんなチームにも「距離を置きたい」「自分のやり方を保ちたい」人は一定数いる。そういう人に無理に関与を求めると、逆に関係がこじれるリスクもある。だからこそ、「巻き込まずとも、機能する仕組みづくり」や「そっと影響を与えるアプローチ」が有効である。
その人の「拒否」の背景を想像する
まず、「一緒にやることを拒む」人の背景はさまざまである。
- 自分のペースや方法を守りたい
- 過去のチーム経験にトラウマがある
- 時間に余裕がない、負担に感じている
- 他者と関わることで評価が下がると感じている(不安)
こうした背景を前提に、「その人の世界を尊重しつつ、遠回しに関わる」アプローチを考えるのが効果的である。
「一緒にやる」ではなく「勝手に使える」形にする
- 誰でも使えるFigmaテンプレートを静かに整備
- ナレッジ共有スライドや「Tips集」をNotionに投稿
- デザインのベストプラクティスを無言で社内Slackにアップ
これらは、強制力がなく、「使いたい人が勝手に使える」ので、抵抗感の少ない関わり方。そして使ってもらえたらラッキー、くらいの温度感で進める。
「教える・関わる」ではなく「参考として見せる」
関与を求めず、「こういうことを自分はしてるよ」と情報として淡々と発信する。
- 自分のFigmaファイルにコメントを丁寧に書いておく(見れば学べる)
- Slackに「今週の学び」を投稿してみる(反応なくてもOK)
- 作業中に「自分はこういうフローでやってます」と自然に口に出す
これにより、相手が心の中で「ちょっと真似してみようかな」と思えばそれで十分。
「関わらなくても大丈夫なチーム構造」をつくる
どうしても巻き込めない相手に時間を割きすぎるより、「巻き込まなくても回る仕組み」をつくる方向も有効的。
- デザインレビューを希望制や「見るだけ参加可」にする
- 共通資産を「必須」ではなく「便利な参考例」にする
- チームの進捗を「全員で話す」より「Notionで見るだけ」にする
こうした構造にしておけば、関与が少ない人でも自分のペースで情報を拾う自由を確保できる。
小さな信頼貯金を積む
関与を拒む人に対しては、日々の些細な場面で「信頼できる味方」であることを示すのが大切である。
- ちょっとしたアウトプットを褒める・感謝する
- その人の得意なことに「教えてほしい」と頼む
- 「この部分すごく参考になります」と素直な称賛を送る
こうした「認知されている・尊重されている」という感覚が、「ちょっとなら協力してみようかな」という気持ちの芽を育てる。
自分が変えられる範囲に集中する
全員を巻き込むことを目標にする必要はない。それは時に時間の浪費や感情の消耗にもなり得る。
- 自分のスタンスを保ち、
- よりよく働ける仕組みを提案し、
- 協力したい人と前向きに進め、
- 様子見の人には「扉を開けておく」
やるべきことはこれで十分。そして時間が経てば、その「拒む人」も、何も言わなくても少しずつ近づいてくることも少なくない。

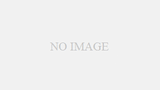
コメント