視認性、誘目性、識別性
サービスやプロダクトをつくる中で、人とのコミュニケーションやミーティングの場でよく耳にする言葉のひとつに「視認性」がある。主に、サービスやプロダクトに触れるユーザーにとって、対象が「見づらくないか」「認識しづらくないか」といったことを判断するための指標のひとつとして使われることが多い。
視認性とは、ひとことで言えば「遠くからでも見やすいこと」を意味する。例えば、街中の交通標識は遠くからでも読みやすい色と配色(安全色彩:色の特性を利用して危険の除去および予防を迅速かつ正確に行うことを目的とした規格:JIS Z9103(2005)安全色一般事項)が使用されており、白と黒、白と青、白と緑などの組み合わせが主に用いられている。特に、黒と黄の組み合わせは最も視認性の高い配色とされており、危険や警告を表す標識によく使われている。
この「視認性」を高めるためには、図と背景色との明るさに差をつける(明度差)ことが重要である。
ちなみに、視認性と似た言葉に「誘目性」「識別性」というものがある。「誘目性」は注意を引き目立つことを指し、赤やオレンジ、黄などの暖色系で鮮やかな色は誘目性が高いとされる。一方、「識別性」は複数の対象の区別のしやすさを示す。例えば、トイレのマークは男女の色の差を大きくすることで識別性を高めている。信号機や交通標識も同様で、色の差をなるべく大きくすることで、人が一見して情報を得られるよう、配色が設計されている。
このように視認性や誘目性、識別性を高めることで、ユーザーに瞬時かつ的確に情報を伝えることができる。
膨張色と収縮色
物理的には同じ大きさでも、実際より大きく見えたり、前に迫って見えたりする色がある。膨張色は明るい色、収縮色は暗い色となり、これらを並べると、同じ大きさでも明るい色の方が膨張して大きく見え、暗い方が収縮して小さく見える。
進出色と後退色
物理的には同じ距離でも、近くにあるように見える色、遠くにあるように見える色がある。進出色は赤、黄などの明るい色、青や紫などの暗い色は後退色に属する。情報を的確に伝えたい場合、視認性だけでなく「距離感」を利用することで、より効果的な配色にすることができるということになる。

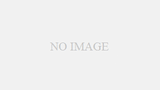
コメント